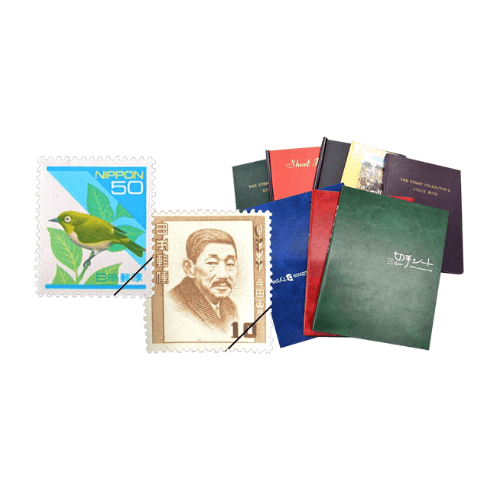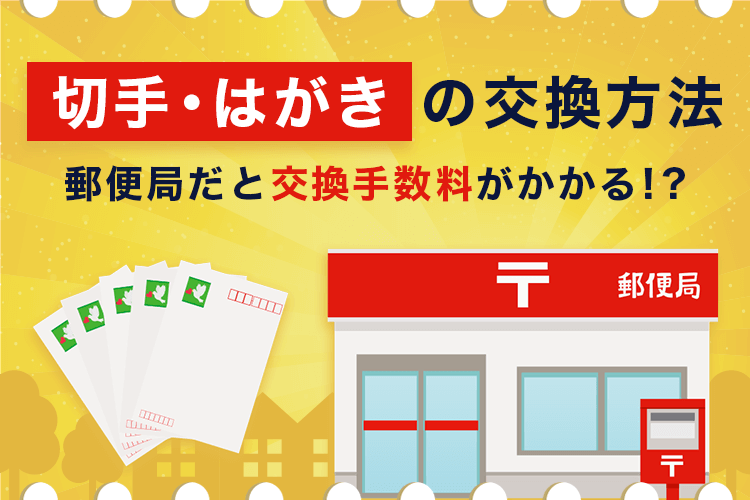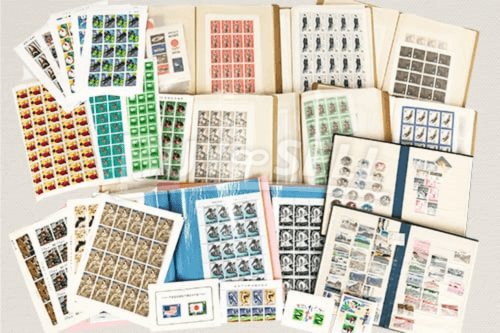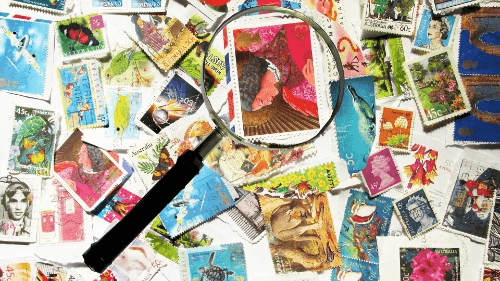はがき料金の値上げ|85円はいつから?古い使わないはがきの活用方法

年賀状・喪中はがき・手紙など、普段の生活ではあまり意識していなくてもはがきや切手を使う機会は意外とあるのではないでしょうか。
度重なる郵便料金の値上げに伴い「なぜ値上げされたの?」「前の額面のはがきって使えるの?交換できる?」など、気になる疑問が多くあるかと思います。
現在の郵便の料金体系や出すときのルール、古いはがきの活用方法をご紹介します。
また、はがきの料金が制定されてきた歴史、はがき料金の値上げが決まった背景についても見ていきましょう。
※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。
目次
はがき料金の沿革
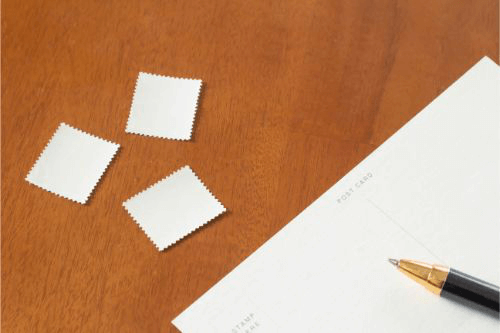
1885〜1949年の間に存在していた逓信省(ていしんしょう)という行政機関は、切手やはがきなど通信に関する機関を幅広く管轄していました。
逓信省の廃止後、戦後間もない1949年に郵政省が創設されたのですが、その当時は2円切手ではがきを送ることができました。
戦後の不況が改善されて景気が回復するとともに物価が徐々に上昇し、1951年以降は5円・7円・10円・20円・30円と切手の料金は値上がりしていきました。
その後、1989年以降のはがき料金の推移は以下の通りです。
・1989年…消費税制度が導入、3%を大幅に超える11円もの値上げ、はがきの切手料金が41円に
・1994年…切手料金50円にまで値上げ
・2014年…消費税が5%から8%の引き上げに伴い、はがきの切手料金は52円切手に
・2017年6月…52円切手から62円切手に大幅値上げ
・2019年10月…消費税率8%から10%にの引き上げに伴い、63円切手に値上げ
・2024年10月…郵便物数の減少により郵便事業の落ち込みを立て直す施策として、85円切手に値上げ
値上げの背景
日本郵政株式会社は、2017年にはがき料金を52円から62円へと大幅に値上げした経緯を、「日本郵便(日本郵政の子会社)の経済状況が悪化しているため」と言及しています。
少子化に伴う人件費の増加、大型郵便の増加による再配達のコスト増大などが原因となり、日本郵便は経済的に逼迫しているとのことです。
その後も、消費税率の引き上げやデジタル化に伴う郵便物数の減少などにより、赤字対策でのはがき料金値上げが続きました。
消費者としては値上げは苦しいところではありますが、郵便事業を独占的に行う日本郵便が倒れることは、国民生活にも大きな影響があります。
郵便サービスを無くしてしまわず、なるべく財布に優しい価格で提供していくためにも、値上げは致し方ないことなのかもしれません。
【2025年更新】郵便サービスの料金システム

2025年現在、はがきと手紙の郵便料金の基本料金は、以下の表の通りとなっています。
| 郵便物の種類 | 基本料金 |
|---|---|
| 通常はがき(定形郵便物) | 85円 |
| 往復はがき(定形郵便物) | 170円 |
| 手紙(定形郵便物)50g以内 | 110円 |
| ミニレター(郵便書簡) | 85円 |
85円の通常はがきのほかにも、往復はがきが170円、定形郵便物の手紙が110円と値上げされています。
定形外郵便物の場合は、表記載の料金と異なるので注意が必要です。
はがきの規定サイズと規格外の料金
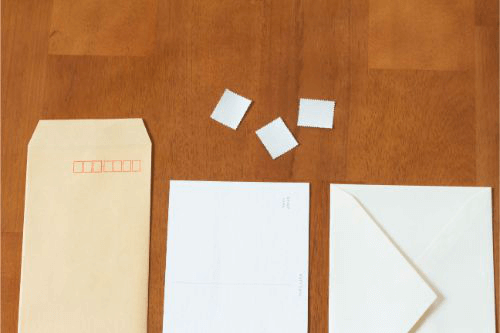
通常はがきは85円で送ることができますが、この85円で送ることができるはがきには、サイズに細かいルールがあります。
通常はがきの規定サイズ
・最小で長辺が14cm以上、短辺が9cm以上
・最大で長辺が15.4cm以下、短辺が10.7cm以下
・重さは2g~6g
ちなみに、郵便局で購入できる普通はがきは、長辺14.8cm×短辺10cmです。
往復はがきでは、このルール内のはがきが2枚繋がっているものである必要があります。
もしも、私製はがきでこれよりも大きいものを送りたい場合には、「第一種郵便物」(封書などと同じ)扱いとなり、その料金を支払わなければなりません。
・長辺が23.5cm以下、短辺が12cm以下、厚さが1cm以下
こちらの規格内であれば、第一種郵便物の定型郵便物として、重さ25g以下なら84円、50g以下なら94円で送ることができます。
これよりもさらに大きいもの、さらに重いものに関しては定型外郵便物として、重さに応じた料金を支払うことになります。
古い(旧料金の)はがきは使える?

料金改定前に発行された52円や62円、63円などのはがきは、今でも使うことができるのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
結論から言うと、郵便料金改定前の古いはがきであっても、現在も引き続き使うことは可能です。
使い方としては、現行料金との差額分の切手を貼るだけです(52円のはがきなら差額33円分)。
切手をベタベタと貼ることで見栄えが良くないのを気にされる場合には、古いはがきは懸賞応募用などに利用し、友人や知人へ出すはがきには新しいはがきを使うなど工夫をしている方が多いようです。
郵便局で有償交換することもできる
郵便局では、使わなくなった額面のはがきや切手を、有料で別の額面のはがきや切手等に交換してくれるサービス(有償交換)を行っています。
交換手数料は以下の通りです。
| 郵便物の種類 | 1枚あたりの手数料 |
|---|---|
| 郵便切手・通常はがき | 6円 |
| 往復はがき・郵便書簡 | 12円 |
| 特定封筒(レターパック) | 55円 |
通常はがきで1枚あたり6円の手数料がかかりますが、この手数料は不要なはがきや切手で支払うこともできます。
はがきが複数枚ある場合には、新たにお金を払うことなく新しいものに交換することも可能でしょう。
この有償交換では、「はがきは使わないから、古いはがきを切手やレターパックに交換したい」ということもできます。
不足分の切手を貼る方法に比べて、手数料がかかる分だけ活用範囲が広くなると言えるでしょう。
使わないはがきは買取がおすすめ
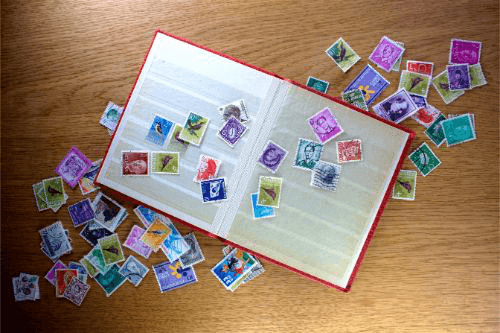
使わなくなったはがきは郵便局で有償交換することもできますが、あくまでも別の郵便サービスへの交換であり、現金化することはできません。
「使わないはがきを現金化したい」という場合には、買取サービスをご利用がおすすめです。
バイセルでは、査定士が利用者の自宅を訪問する「出張買取」や、宅配キットを使って売りたい品物を買取業者に送付する「宅配買取」など、利用者の生活スタイルに合わせて便利な買取方法を選ぶことができます。
出張買取なら梱包・発送する手間さえありませんので、大量のはがきを売りたい人にも非常に利便性の高い方法と言えるでしょう。
マナーや査定に関する厳しい研修を受けたバイセルの査定士が、1点1点しっかりと見させていただきます。
出張料・査定料・キャンセル料などの各種手数料は無料ですので、「試しに査定だけ」といった場合にも費用の心配なくご利用いただけます。
まずはお気軽にバイセルの無料査定をお試しください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら
切手買取をもっと見る
郵便の便利なオプション(速達など)の料金について
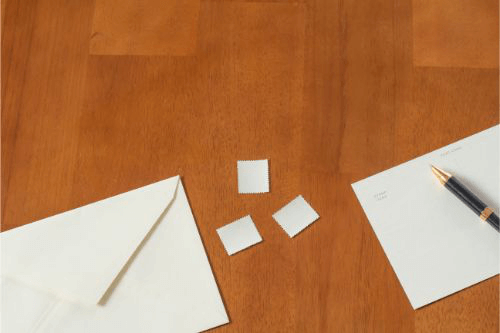
はがきを含めて重要な郵便物を送る場合には、様々なオプションサービスをつけることができます。
郵便の主なオプションサービスには以下の4つがあります。
・速達
・一般書留
・簡易書留
・特定記録
これらのオプションサービスの料金も値上げしているため、利用時には注意が必要です。
基本的にはがきの使い道はないが、利用できるオプションを知っておけば、活用の幅が広がるかもしれません。
それぞれのサービス内容と料金についてご紹介します。
速達
速達とは、郵便物を通常より早く届けてもらえるサービスです。
発送元と届け先の地域によって日数は変わりますが、速達を利用すれば基本的に1〜3日で届けられるでしょう。
通常郵便より早く届けられる分、割り増し料金がかかります。
・重さ250gまで…通常の郵便料金に+290円
・重さ1kgまで…通常の郵便料金に+390円
・重さ4kgまで…通常の郵便料金に+660円
料金は通常の郵便料金に上乗せする形になるので、通常はがきを速達で送りたい場合の料金は、以下のような計算方法になります。
85円+300円=385円
なお、窓口対応ではなくポスト投函で速達を利用したい場合には、はがき右上部に赤い線を引いたうえで、(郵便局で購入したはがきの場合には印字済みの切手代も含めて)385円分の切手を貼れば速達で対応してくれます。
一般書留
書留とは、配達までの送達過程が記録され、破損したり届かなかったりした場合に補償してもらえるサービスのことです。
現金以外の貴重品を送る際などに利用されることが多い「一般書留」は、通常の郵便料金プラス480円を支払えば、10万円まで保証してもらえます。
通常はがきを書留で送る場合の料金は、以下のような計算方法になります。
85円+480円=565円
書留は、郵便局に備え付けの「書留・特定記録郵便物等差出票」を記入して窓口に持っていくことで、利用することができます。
簡易書留
簡易書留は、書留同様に送達過程が記録され、何かあった際に補償をしてくれるサービスです。
書留と違う点は、オプション料金が通常の郵便料金プラス350円と安い代わりに、補償額が5万円となっています。
普通はがきで発送するには不安だけど、書留をするほどではない場合などに最適と言えるでしょう。
通常はがき簡易書留で送った場合の料金は、以下のような計算方法になります。
85円+350円=435円
利用方法は一般書留と同じく、郵便局に備え付けの「書留・特定記録郵便物等差出票」を記入して窓口に持っていくことで利用することができます。
特定記録
特定記録とは、発送したことの記録や受け取りの記録が確認できるサービスのことです。
個人間ではあまり使わないかも知れませんが、必ず受け取って欲しい郵便物などに付けることが多いサービスでしょう。
書留のような補償がないため料金もその分安く、郵便料金にプラス210円となっています。
通常はがきを特定記録で送った場合の料金は、以下のような計算方法になります。
85円+210円=223円
利用方法は書留と同じく、郵便局に備え付けの「書留・特定記録郵便物等差出票」を記入して窓口に持っていくことで利用することができます。
年賀状の料金についての豆知識
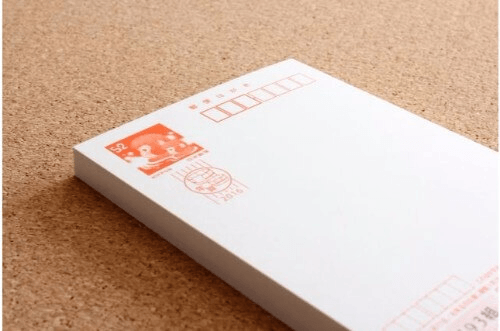
はがきを最も使うタイミングと言えば年賀状シーズンではないかと思います。
最後に、年賀状に関するちょっとした豆知識をご紹介します。
通常はがきと年賀状の料金は違う?
はがきの料金は85円ですから、年賀状の価格も当然85円ではないかと思われるかもしれません。
たしかに2024年用の年賀状などを見ると、無地・くぼみ入り(目の不自由な方が上下・表裏を区別できるよう、おもて面左下に半円のくぼみが入っている)・インクジェット紙(無地)・ディズニーコラボなどの各種年賀状の価格は85円となっています。
しかしながら、一部価格が85円でない年賀状も存在しています。
通常はがきと異なる価格の年賀状の種類を、いくつかご紹介します。
インクジェット紙 写真用
写真用のインクジェット紙で作られた年賀状は、デジタルカメラなどで撮影した写真の印刷に適したはがきで、通常のインクジェット紙に比べて光沢感が強く、鮮やかな発色が可能となっています。
特殊な紙を使用している分、料金が高くなっています。
寄付金付絵入り年賀はがき
「寄付金付絵入り年賀はがき」は、はがき1購入ごとに寄付ができる年賀はがきです。
寄付金が含まれている分、通常の年賀はがきよりも高めの料金になっています。
集められた寄付金は公募から選ばれた社会貢献事業などの活動に配分され役立てられます。
全国版と地方版(27種類)があり、全国版なら「龍と彩雲」、北海道版なら「エゾモモンガ」など、それぞれの地域や都道府県によって異なる絵柄が印刷されています。
広告付年賀はがき
「広告付年賀はがき」とは、一部の地域における限定販売で、企業などの広告が掲載されている年賀はがきのことです。
広告が入っていることで価格が安く抑えられています。
はがき料金の値上げには移行期があった
2017年にはがきの料金が52円から62円に値上がりしました。
この値上げは6月1日から行われたのですが、実は「2017年12月15日から2018年1月7日の間に出された2018年の年賀状を除く」という特例が設けられました。
したがって、年賀はがきに関しては2019年のお正月分から値上げがされたことになります。