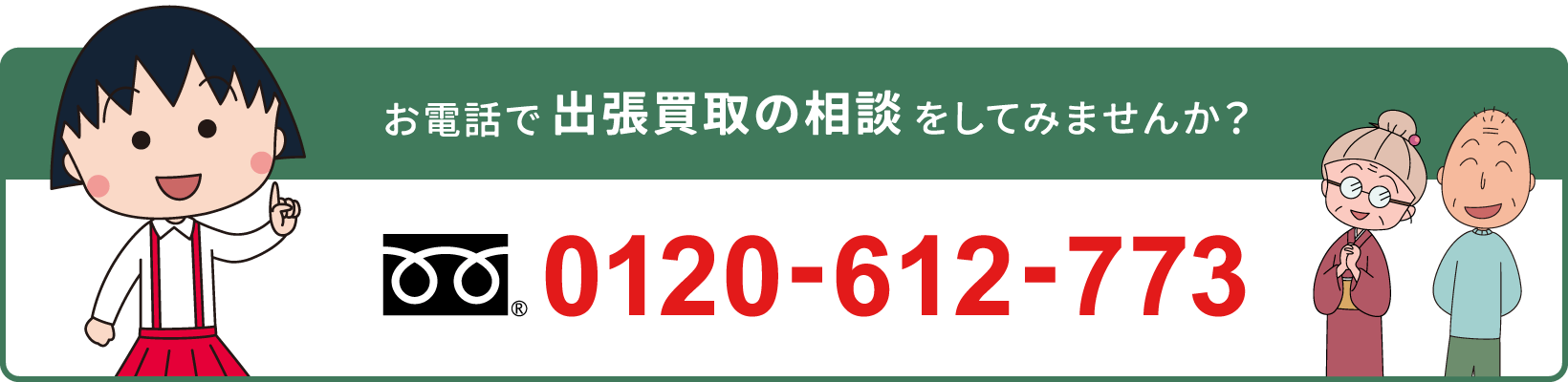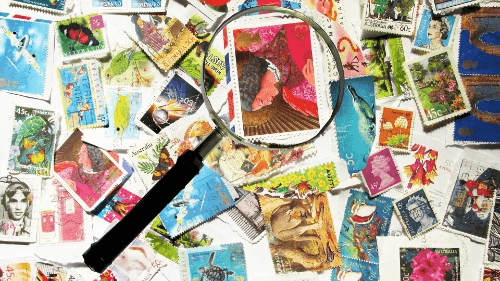簡易書留を切手払いで送るときの注意点!おつりは返ってくる?送料を安く抑えるには?

簡易書留は重要な書類を送りたいときや、宛先側に荷物が届いたのかを確認したいときに使えます。
郵便局の窓口で手続きをする際には送料を現金で支払うことが多いですが、自宅に余っていた切手がある方は簡易書留の利用料金に充てることができます。
本記事では簡易書留を切手払いで送るときの注意点や、簡易書留を出す具体的な利用方法、そして送料を安く抑えるポイントをご紹介します。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。
簡易書留を切手払いで送るときの注意点
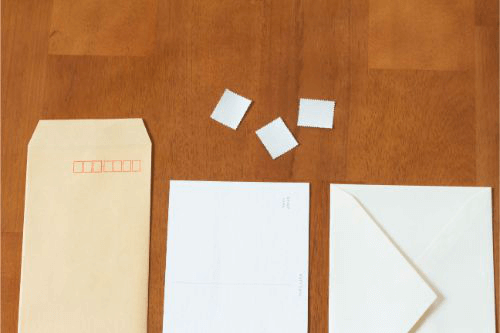
「額面を間違えて買ってしまった切手が残っている」「普通切手を何枚か持ってるけど使うタイミングがない」という方は、簡易書留の利用料金に充てることができます 簡易書留を切手払いで送る際にはいくつか注意点があるのでご紹介します。
おつりは返ってこない
簡易書留は切手払いができますが、全ての郵便サービスは送料以上の額面を切手で支払ってもおつりが返ってきません。
そのため、簡易書留の支払いには現金とお持ちの切手を併用することをおすすめします。
たとえば郵便局の窓口で簡易書留料金320円を支払う場合は、310円を切手で、10円を現金で払えば余った切手を使い切れるでしょう。
料金別納は切手払いではなく現金払いのみ使える
料金別納とは、10通(個)以上の郵便物や荷物を送る際に利用できる簡易書留の送料を一括で支払う方法です。
料金別納の切手支払いは2018年で廃止され、現金払いになったため間違えないようにしましょう。
簡易書留は必ず郵便局の窓口から出す
簡易書留はポストへの投函やコンビニの受付ができず、郵便局の窓口からでないと送れません。
切手を貼った状態でポストに投函すると、簡易書留ではなく一般郵便として扱われてしまい、簡易書留のサービスである「送達過程の記録」と「トラブル時の補償」の対応がされません。
簡易書留を切手払いで送る際には、必ず郵便局の窓口で手続きをしましょう。
送料を安く抑えられる書留はどれ?

「書留」とは日本郵便が提供しているオプションサービスの1つで、簡易書留・一般書留・現金書留の3種類があります。
引き受けから配達までの送達過程を記録し、郵便物(手紙・はがき)などが壊れたり届かなかったりした場合は損害要償額の範囲内で実損額を賠償できます。
送達過程とは、具体的には「荷物を郵便局に出した時間」「荷物が到着した郵便局の場所や時間」「荷物を配達した時間」などが挙げられます。
荷物には追跡番号が付けられ、インターネットで配達状況を確認できます。
さらに、書留は配達員から受取人への手渡しで、受け取り時にはサインが必要なので届いていないかと心配する必要がありません。
書留の中でも、「なるべく送料を抑えたい」という際には利用料金が350円の簡易書留が適しています。
ただし、書留の種類ごとに送達過程に記録内容や郵送するものが異なるので、以下で確認しておきましょう。
簡易書留の特徴と利用方法
簡易書留は、利用料金が350円と書留の中で最も安いです。
送達過程は「宅配物の引き受け」と「配達」のときだけ記録されます。
郵便物が紛失したなどのトラブルによる損害要償額は最高5万円までです。
また、受取人に手渡ししてもらえることも特徴で、受取人が不在の場合でも夜間に郵便局で受け取れます。
利用の際には郵便料金にプラスで簡易書留代を支払います。
「重要ではないけど配達されているか確認したい荷物がある」「なるべく送料を抑えたい」という際に便利です。
簡易書留は現金と切手で支払う方法があり、それぞれの利用方法と注意点を説明します。
現金で支払う
簡易書留を現金で支払う場合は、料金が印字された「郵便証紙」を貼り付けて窓口に差し出せば手続きしてくれます。
郵便証紙の発行は窓口の担当員が行っているので、現金払いを希望する場合は簡易書留でと伝えればOKです。
切手で支払う
簡易書留は切手で支払いできます。
郵便証紙の代わりに切手を封筒などに貼り付けることで利用できます。
切手支払いの際は送料を自分で計算するか、郵便局の担当員に計算してもらって必要分の切手を貼って窓口に差し出します。
送料の金額によっては切手を何枚も貼り付ける必要があります。
一般書留と現金書留との違い
簡易書留は料金が安く送達過程が「宅配物の引き受け」「配達」のみ記録というのが大きな特徴ですが、一般書留と現金書留との違いも気になりますよね。
一般書留と現金書留、それぞれの特徴を解説します。
一般書留
一般書留は、引き受けから配達が完了するまでの送達過程を全て記録します。
基本料金にプラス480円を払えば一般書留を利用できます。
損害時の補償額の最高額は10万円です。
一般書留は簡易書留よりも補償上限額が高いため、重要な書類や高価なものを送りたいときに利用するといいでしょう。
現金書留
現金書留は、現金を郵送する際に利用できます。
のし袋ほどのサイズのため、ご祝儀などを送るときにちょうどいいでしょう。
現金書留は基本料金にプラス480円を支払います。
送達過程の記録や補償内容は一般書留と同じですが、現金書留は損害要償額が1万円までです。

より詳しい情報を知りたい方はこちら
切手買取をもっと見る