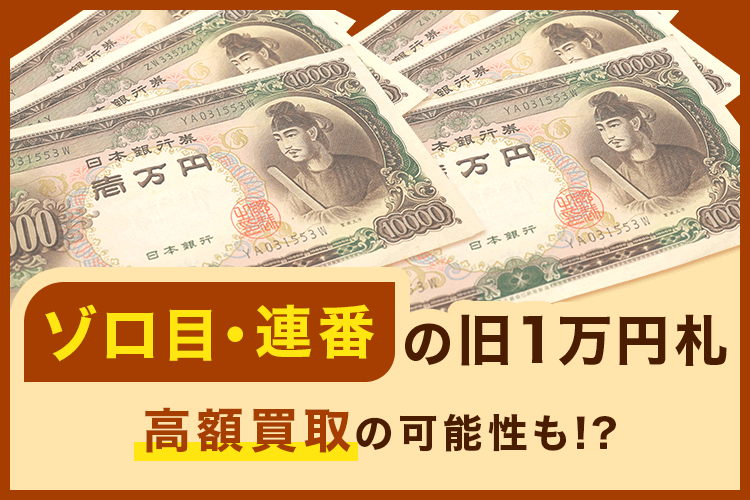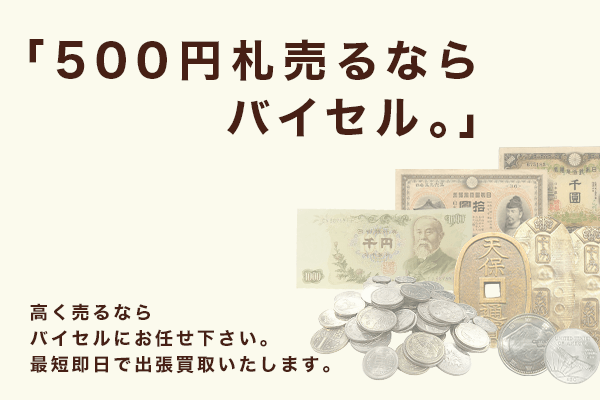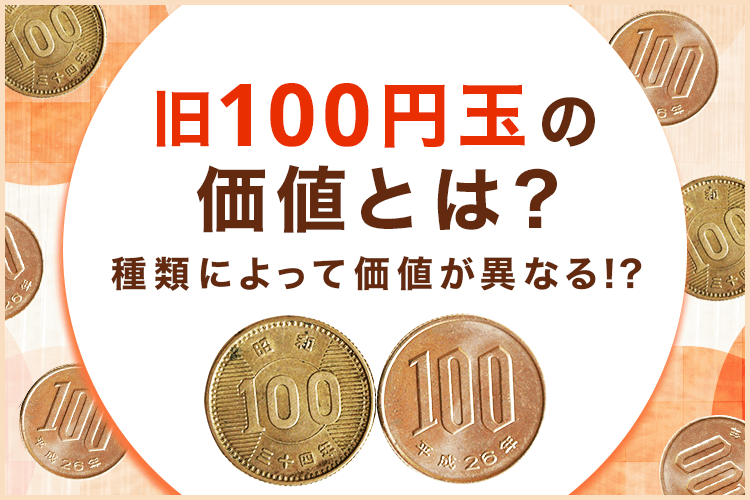聖徳太子の一万円札、価値は?旧札の買取相場と高く売れるレア番号を解説

ご自宅のタンスや引き出しに、聖徳太子が描かれた古い一万円札が眠っていませんか?「昔のお金だけど、今でも使えるの?」「もしかして、額面以上の価値がある?」と、その価値について気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、旧一万円札は現在も10,000円として使用できますが、その多くは額面通りの価値です。しかし、ピン札(未使用の綺麗な状態)であったり、記番号が珍しいものや印刷エラーがある紙幣は、古銭として高い価値を持ち、高価買取が期待できます。
この記事では、聖徳太子の一万円札をはじめとする旧札の種類、額面以上の買取価格がつくレアな紙幣の特徴と買取相場、そして1円でも高く売るための重要なコツを専門家が分かりやすく解説します。
掲載品の買取に関するお知らせ
一部掲載品については買取が難しい場合がございます。
詳しくはオペレーターまでお問い合わせください。
※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。


「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!
価値が見込める旧一万円札の特徴と買取相場
一般的な旧一万円札の価値は額面通りですが、以下の特徴を持つものは「プレミア紙幣」としてコレクターからの需要が高く、高価買取の対象となります。
1. 記番号が珍しい(ゾロ目・AA券など)
紙幣の左上と右下に印刷されているアルファベットと数字の組み合わせ(記番号)は、価値を大きく左右するポイントです。
- ゾロ目:「111111」や「888888」など、すべての数字が同じもの。特にラッキーセブンとされる「777777」は人気があります。
- キリ番:「100000」や「500000」など、キリの良い数字のものです。
- 階段:「123456」のように数字が順番に並んでいるものです。
- AA券:記番号の最初と最後のアルファベットが「A」で挟まれているもの(例:A123456A)。その紙幣で最初に印刷されたグループのため、希少価値があります。
- ZZ-Z券:記番号の最後が「Z」で終わる、最終グループの紙幣です。(例:ZZ123456Z)
これらの珍番号紙幣の価値は一概には言えませんが、買取相場は額面通りから数十倍になる可能性があります。特に希少な最初期の「AA券」や最終期の「ZZ-Z券」は、額面の10倍前後で取引されることもあります。
2. エラープリントや福耳がある
製造過程で発生したエラーがある紙幣は、非常に希少価値が高くなります。
- エラープリント:印刷がズレている、インクが滲んでいる、一部の印刷が欠けている、裏写りしているなどのエラーがある紙幣。
- 福耳付き:裁断ミスのため、紙幣の角に余分な紙片(福耳)が付いているもの。
エラープリント紙幣は市場に出回ることが極めて稀なため、非常に高い価値がつきます。エラーの種類や度合いによりますが、買取相場は額面の10倍から、時には100倍以上に達することもあります。同じく裁断ミスである福耳付きの紙幣も、額面の数十倍の価値がつくことがある希少品です。
3. 状態が非常に良い「ピン札」
「ピン札」とは、発行されてから一度も使用されていない、折り目やシワ、汚れが一切ない新品同様の状態の紙幣を指します。古紙幣の査定において状態は極めて重要で、同じ珍番号やエラー紙幣でも、ピン札であるかどうかで買取価格が数倍変わることも珍しくありません。逆に、折れ目や汚れがあると価値が大幅に下がってしまうため注意が必要です。
※上記の買取相場はあくまで参考情報であり、実際の買取価格を保証するものではありません。お品物の状態や市場の状況によって買取価格は変動します。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ買取対象となる旧一万円札の種類
これまで日本で発行された旧一万円札は、聖徳太子と福沢諭吉の肖像が描かれた3種類です。
聖徳太子 一万円札(C号券)
1958年(昭和33年)から発行された、日本初の壱万円札です。表面に聖徳太子、裏面に鳳凰が描かれています。多くの人が「古い一万円札」としてイメージする、非常に知名度の高い紙幣です。
福沢諭吉 一万円札(D号券)
1984年(昭和59年)から発行された、福沢諭吉が初めて肖像となった紙幣です。裏面には日本の国鳥であるキジが2羽描かれています。
福沢諭吉 一万円札(E号券)
2004年(平成16年)から発行された紙幣で、D号券からデザインが変更され、ホログラムなど多くの偽造防止技術が導入されました。裏面のデザインは平等院鳳凰堂の鳳凰像です。
旧一万円札を1円でも高く売るためのポイント
古銭の価値がわかる専門業者に査定を依頼する
旧一万円札の価値は、ただ古いだけでは決まりません。記番号の希少性やエラーの有無、市場での需要など、専門的な知識がなければ正確な価値を判断するのは困難です。銀行に持って行けば額面通りの10,000円にしかなりませんが、古銭専門の買取業者であれば、紙幣の持つプレミア価値までしっかりと見極めてくれます。
綺麗な状態を保つ【自分で洗浄しない】
古い紙幣は非常にデリケートです。汚れやシミがあっても、自分で洗ったり拭いたりしないでください。シワや破れの原因となり、価値を大きく下げてしまう可能性があります。現状のまま査定に出すことが最も重要です。
鑑定書や付属品があれば一緒に提出する
もし購入時のケースや鑑定書が残っていれば、必ず紙幣と一緒に査定に出しましょう。本物であることの証明となり、査定額のアップに繋がります。
旧一万円札の買取はバイセルへご相談ください
バイセルには、古銭に関する深い知識と豊富な査定経験を持つ査定士が多数在籍しています。お持ちの聖徳太子の一万円札や古い福沢諭吉の一万円札に、思わぬ価値が隠れているかもしれません。「この番号はレア?」「エラー紙幣かもしれない」など、気になる点がございましたら、ぜひお気軽にバイセルの無料査定をご利用ください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら
古銭買取をもっと見る
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ