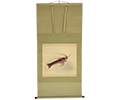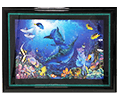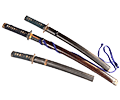骨董品買取で税金はかかる?後悔しないための注意点を押さえておこう

絵画や陶磁器、茶器といった骨董品の買取をお考えですか?
骨董品の買取にあたって、どこに買取に出せば良いのか、どれくらいの買取価格がつくのか、というのは当然気になるポイントでしょう。
しかしながら、安心して買取サービスを利用するには買取方法や買取価格だけではなく、骨董品買取に関わってくる税金についても知っておきたいところです。
骨董品買取に関わる税金について知っておかなければ、買取してもらった後に思わぬトラブルを生む可能性があります。
骨董品買取に関わる税金の概要や課税対象となる条件に加えて、税金額の計算方法や種々の注意点についてもご紹介します。
※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。


「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!
目次
骨董品買取で税金はかかる?
骨董品を売ると買取金額を受け取れますが、税金はかかるのでしょうか。
一言で答えるならば「場合によっては税金がかかる」ということになります。
では、骨董品の買取が課税対象になるのはどのような場合でしょうか。
骨董品1個の価額が30万円以下だと非課税
骨董品を売って利益を得た場合でも、1個または1組の価額が30万円以下であれば課税対象にはなりません。
骨董品を含む資産の譲渡による所得は、「譲渡所得」として課税対象になると所得税法に定められています。
ただし、骨董品の中でも「1個又は1組の価額が30万円以下」のものは生活用動産とみなされ、課税対象から外されます。
家具や通勤用の自動車、衣服など、生活に通常必要と考えられる動産の譲渡による所得は、「生活用動産の譲渡による所得」として非課税という特例があるからです。
骨董品1点の価額が30万円以上だと課税対象
骨董品の買取で課税対象となるのは「1個又は1組の価額が30万円を超えるもの」を売却した場合です。
絵画・ブロンズ像・陶磁器・茶器など、骨董品の種類は問いません。
茶道具などで実用しているものであったとしても、その品物の歴史的価値や希少性によって30万円を超える価額がつけば課税対象です。
譲渡所得があったら必ず確定申告を!
課税対象となる譲渡所得があれば必ず確定申告をしましょう。
申告を行わないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられます。
場合によっては重大な犯罪として、500万円以下の罰金や5年以下の懲役が科せられる可能性があるため必ず申告しましょう。
なお、課税対象となる譲渡を行ったとしても、確定申告による計算の結果、課税額が0円となる可能性もあります。
課税対象かどうかの基準は「価額」であって売った金額ではない
前項目で「1個又は1組の価額が30万円を超える」骨董品の買取は、所得税の課税対象だと説明しました。
この「価額」とは「その品物の客観的な価値に相当する金額」を表す税法上の用語です。
「30万円を超えた場合に」というのは実際に売った金額のことではなく、「客観的に見てその品物が持っている価値」の話です。
買取業者を相手にわざわざ安く売却する人はいないと思いますが、たとえば骨董品を知り合いに売却する場合を考えてみましょう。
例えば、「客観的に見れば40万円の価値がある絵画だけど、親しい相手なので25万円で売却した」とします。
この場合、売却価格は25万円ですが、価額が30万円を超えるため課税対象となるのです。
個別のケースで課税・非課税の判断がつかない場合は、信頼できる税理士に確認するのも良いでしょう。
骨董品の買取における譲渡所得とは
骨董品を買取に出して発生した所得は、税法上「譲渡所得」に分類されます。
譲渡所得とは、所得税における所得の区分の一つです。
資産の譲渡による所得を指し、骨董品のほかに土地・建物・借地権・宝石・金地金・船舶・ゴルフ会員権などの譲渡による所得も含まれます。
税金の計算を行うときには、骨董品以外の資産の譲渡についても考慮する必要があるため注意しましょう。
譲渡所得にならない場合がある
ただし、資産の譲渡による所得であっても、以下に挙げたものは例外的に譲渡所得には含まれません。
雑所得に分類されるもの
- 棚卸資産(※1)の譲渡による所得
- 営利目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得(※2)
- 金銭債権の譲渡による所得
(※1)商品や仕掛品など、販売目的と何らかの形で結びついている財やサービス
(※2)事業として届出をしている場合には事業所得になる
山林所得に分類されるもの
- 山林の伐採又は譲渡による所得
つまり、営利目的でない個人が行った骨董品の買取による所得は、課税・非課税の差はあれど、通常すべて譲渡所得に分類されます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得
さらに譲渡所得は、当該資産の所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれます。
所有期間の詳細な規定は資産の種類によって異なるので、ここでは骨董品の場合に絞ってご紹介します。
骨董品の譲渡では、
- ・短期譲渡所得…取得したときから売却したときまでの所有期間が5年以内
- ・長期譲渡所得…取得したときから売却したときまでの所有期間が5年以上
税金の計算上、この短期譲渡所得と長期譲渡所得は分けて考えることになります。
譲渡所得の計算方法と特別控除
税制上の譲渡所得金額の計算方法についてご紹介します。
譲渡した資産が土地・建物であった場合には計算方法が異なりますが、ここでは骨董品を含む「土地・建物以外の資産」についてのみご紹介します。
また説明の都合上、課税対象にならない譲渡は含まないものとします。
譲渡所得金額は、その年の1月1日から12月31日までという1年間の合計で算出されます。
ある年の譲渡所得金額の計算方法
ある年の譲渡所得金額は一般に、譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)という式で出せます。
取得費とは骨董品の購入代金で、譲渡費用とは売るためにかかった費用です。
譲渡費用は、買取業者に支払った出張費や査定料などの手数料も含まれますので、見積書や領収書はきちんと取っておきましょう。
資産の譲渡が1年間に複数回あった場合には、譲渡価額・取得費・譲渡費用は1年分の合計額で計算します。
税金を計算する上での譲渡所得金額の計算方法
そして、税金の計算をする上での譲渡所得金額は、税制上の譲渡所得金額=短期譲渡所得金額+長期譲渡所得金額×1/2−50万円という式で計算されます。
この50万円は特別控除として、税金の計算上控除されます。
なお、短期譲渡所得金額+長期譲渡所得金額×1/2が50万円に満たないときは、その合計金額までしか控除されません。
例えば、1年間に「3年所有した価額50万円の絵画(取得費25万円)」と、「6年所有した価額100万円の陶磁器(取得費60万円)」を譲渡したとしましょう(譲渡費用はかからなかったものとします)。
すると短期譲渡所得金額は50万円−25万円=25万円、長期譲渡所得金額は100万円−60万円=40万円となります。
この例における税制上の譲渡所得金額は、25万円+40万円×1/2=45万円です。
控除前の譲渡所得金額が50万円未満ですので、45万円が控除されます。
その結果税計算上の譲渡所得は0円となるため、税金はかからないということになります。
骨董品買取による譲渡所得は総合課税
骨董品買取による譲渡所得は、規定の計算方法によって金額が算出されます。
そして、算出された譲渡所得金額は総合課税の対象となります。
つまり、給与所得や事業所得など、総合課税される他の所得と合わせて計算された上で、所得税の課税・非課税、あるいは課税額が決まります。
具体的な税金額については、総合課税される所得の合計から所得控除額を控除し、それに税率を乗じて算出することができます。
所得控除額や税率の詳細については、国税庁のホームページ等を参照してください。
骨董品買取で損失があっても損益通算はできない
骨董品買取による譲渡所得は総合課税の対象として他の所得とあわせて税計算されます。
ただし、骨董品買取で損失があった場合(売却時の価額が取得費よりも安かった場合)でも、他の所得と相殺(損益通算)はできません。
これは税制上「生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他の所得と相殺できない」とされているからです。
骨董品の売却で所得が出たら住民税や国民健康保険料はどうなる?
価額30万円を超える骨董品の買取によって譲渡所得があれば、当然ながら譲渡所得も含めた上で住民税や国民健康保険料の金額が計算されます。
毎年の給与所得や事業所得等に加えて、臨時的に譲渡所得があった場合にも住民税や国民健康保険料の金額も上がることが予想されます。
中には知らないまま、住民税や国民健康健康保険料の納付書を見て驚く人もいるようです。
ご存知の方も多いと思いますが、住民税や国民健康保険料の金額は前年の所得に基づいて算出されます。
一般的に、前年の所得が多ければ住民税や国民健康保険料の金額も高く、前年の所得が少なければ住民税や国民健康保険料の金額も低くなります。
価値の高い骨董品を買取に出す際には、譲渡所得がさまざまな税金等と関係しているのだと知っておきましょう。
骨董品の売り方によって節税は可能?
ここまで見てきたように、骨董品の売却による譲渡所得の金額によって総合課税の所得税率や住民税額、国民健康保険料が変わってきます。
そのため一般的には、売りたい骨董品が複数ある場合、長い年月をかけて少しずつ売却していくことで、支払う税金や国民健康保険料を節約できる可能性があります。
この場合、特別控除額の50万円を毎年使うことができるのもポイントです。
ただし、ここで注意しなければならないのが、骨董品の価値は不変ではないということです。
骨董品の価値は保存状態や市場動向にも左右されますから、「節税のために」と置いているうちに価値が下がってしまう可能性があります。
いくら節税できても、骨董品の買取価格自体が低くなってしまっては意味がありませんよね。
そこでまずはバイセルの無料査定でお持ちの骨董品の価値を確かめたうえで、節税対策をするべきかどうか検討してみるのがおすすめです。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ骨董品を相続した場合の税金はどうなる?
「親がコレクションしていた」などで、骨董品を相続する場合もあるでしょう。
ここでは、相続した骨董品について、
- 骨董品を相続すると相続税はかかる?
- 相続した骨董品を売却した場合の所得金額の計算方法は?
- 骨董品を持っていると固定資産税はかかる?
といった疑問についてお答えしていきます。
骨董品を相続すると相続税はかかる?
相続税とは、死亡した人の財産を相続や遺贈するとかかる税金です。
相続税において財産とは、現預金や有価証券に加えて金銭的に見積もることができる経済的価値のある全てのものを指し、骨董品も含まれます。
そのため、骨董品も相続税の課税対象です。
ただし相続税には、相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)という基礎控除額の規定があります。
骨董品を含めて、相続される財産の合計額が基礎控除額以下なら、相続税の申告と納税は必要ありません。
相続した骨董品を売却した場合の所得金額の計算方法は?
骨董品を売却した時の譲渡所得の金額は、譲渡価額−(取得費+譲渡費用)で求めることができました。
この「取得費」ですが、相続した骨董品の場合には自分で購入したわけではありませんよね。
相続した骨董品の取得費がどうなるかと言うと、「亡くなった方が取得した時の価格」がそのまま引き継がれて使われます。
相続した骨董品の購入記録等がある場合には、売却後の税計算に使える場合があるため残しておきましょう。
相続した骨董品の購入額が分からない場合
とはいえ、亡くなった方がいくらで購入したかは分からない場合もありますよね。
その場合には、取得費は「売却価格の5%」とみなされてしまいます。
たとえば骨董品が100万円で売れたとしたら、取得費はその5%である5万円、つまり譲渡所得金額は(譲渡費用がかからなかったとすると)95万円ということになります。
実際には購入時の20倍もの価格で売れることは稀であることを考えると、厳しいルールであると言えます。
こうなると税負担も重くなってしまいますので、骨董品の購入記録がある場合は捨てずに保管しておきましょう。
骨董品を持っていると固定資産税はかかる?
土地や建物を所有している場合には、持っているだけで固定資産税がかかります。
しかし、骨董品は税法上の固定資産には含まれませんから、所有していても税金はかかりません。
NFTアートを売却した場合の税金はどうなる?
通常の絵画を売却した場合には、ここまでお話してきた通り、譲渡所得として総合課税されます。
では、触れられる現物がないNFTアートの場合にはどのようなルールになっているでしょうか。
実はNFTアートを売却した場合でも、通常の絵画と同じように譲渡所得として総合課税されます。
営利目的で継続的に行われた場合には雑所得や事業所得として扱われる点も同様です。
骨董品の買取にかかる税金についてのまとめ
最後に、骨董品の買取と税金について注意したい点をまとめておきましょう。
- 1点の買取金額(価額)が30万円を超えると譲渡所得として課税対象になる
- 譲渡所得があった場合は確定申告が必要になる
- 年間の譲渡所得の合計額で税計算される
- 他の所得と合わせて総合課税の対象になる
- 譲渡所得の金額によっては住民税や国民健康保険料に影響することもある
骨董品の買取にかかる税金のルールをしっかり押さえておき、申告漏れなどでペナルティを受けることのないようにしましょう。

より詳しい情報を知りたい方はこちら
骨董品買取をもっと見る
こんなコラムも読まれています
- 家の壺が高額で売れるかも?買取相場や高く売れやすい種類を解説!
- 陶磁器とは?焼き物の素材別の特徴や高値がつきやすい作品を見分けるコツを解説
- 骨董品買取|相場一覧表と買取対象品、おすすめの買取方法など徹底解説
- 現代アートの買取相場は?買取対象の作家や高く売るポイントをご紹介!
- 骨董品を高く売るための4つのコツ!売却時の注意点や買取方法を紹介
- 江戸切子の買取相場はいくらぐらい?模様の種類や高額買取のための5つのポイント
- 赤珊瑚の本物と偽物の見分け方は?価値が決まるポイントや保管方法も解説
- 海外の有名な現代アート作家15人!世界的な日本人アーティスト19人も紹介
- 絵画の種類には何がある?技法・流派・題材などによる分類を一覧で紹介
- ブランド品・時計の買取で税金はかかる?確定申告はいくらから必要か