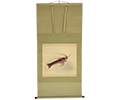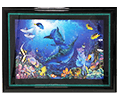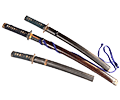日常生活で掛け軸を親しむための方法!掛け軸の楽しみ方や場所を知ろう

掛け軸は、普段あまり目にしない人にとっては、さほど親しみのないものでしょう。
しかしながら、美しい花の絵や水墨画などをよく見てみると「きれい」「面白い」「癒される」などと思えるかもしれませんよ。
では、実際に日常生活において、どのような場面で掛け軸を楽しむことができるのでしょうか。
本記事では、日常で掛け軸に親しむための方法をいくつかご紹介しますので、ぜひ参考にご覧ください。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。
掛け軸の基礎知識

掛け軸は、10世紀後半から中国で普及し始め、はじまりは仏教における礼拝用に用いられていました。
日本にも仏教と掛け軸が普及し、茶の湯(茶道)において書や絵画を壁に飾る風習が生まれました。
茶室に掛けられる掛け軸は「茶掛」「掛物」などと言われ、茶席を設ける主人からの想いが込められています。
現在は、和室の床の間にインテリア・鑑賞用として掛ける人も多く、幅広い用途で楽しまれています。
ちなみに、掛け軸の数え方は「幅(ふく)」で、一幅(いっぷく)、二幅(にふく)、三幅対(さんぷく)…と数えていきます。
掛け軸の親しみ方①床の間を活用する
ご自宅に和室の一部に床の間があるという方は、せっかくなら掛け軸を飾りませんか。
掛け軸は高いものから安いものまで、さらに書画・絵画など種類もさまざまです。
絵の部分だけを変えられるようになっているものもありますので、春は桜、夏はひまわり、秋は紅葉、冬は南天など季節にふさわしいものを飾るのも良いでしょう。
掛け軸初心者の方は、まずはリーズナブルなものを購入して、気軽に飾って楽しむというところから始めてみてはいかがでしょうか。
家を訪ねてきたお客さんに和室に上がってもらった際に、掛け軸について「きれい」「風情がある」などと言われると嬉しいものです。
飾っているうちに「次は丁寧に描かれた墨絵が良い」「ちょっとくらい高くても見映えがするものが良い」など、段々とこだわりが出てきたら上質なものに挑戦してみるのも良いですね。
少し値の張る物を飾ることで、高級感のある空間を演出できます。
掛け軸の親しみ方②お寺に行ってみる
お寺によく行くという方はお気付きかもしれませんが、お寺の室内の床の間には掛け軸が飾られているところもあります。
ぜひ休日にお寺に行った際には床の間をチェックしてみてください。
掛け軸に親しみを持つことは、お寺を訪れる一つの楽しみにもなるでしょう。
お寺にはあまり行かないという方も、掛け軸の鑑賞がてら出かけてみませんか。
何度も訪れるたびに、掛け軸の書や絵が変えられているはずです。
春には桜、秋には紅葉など、時期にふさわしい掛け軸が飾られた床の間は、季節の移り変わりを感じさせてくれます。
また、お寺ごとに飾られている掛け軸は全く違いますので、お寺めぐりをするといろいろな掛け軸に出会えるので楽しいですよ。
以下ページより、バイセルの掛け軸の買取実績をご覧いただけます。
どのような掛け軸が価値が高いのか、高く売れるのか、知りたい方はぜひお読みください。
掛け軸の親しみ方③お茶会に参加する
お茶会では点てられたお茶とお菓子を食べるだけではありません。
お茶室にある床の間には季節にふさわしい生け花と掛け軸が飾られます。
そして、お茶会の始めには、必ず花と掛け軸について紹介があります。
お茶を飲む前に掛け軸について話を聞くことで、知識が増え、より興味が湧くかもしれません。
お茶会当日の話は帰ってからメモしておくと、今後掛け軸を選ぶ際などの参考にしやすいでしょう。
お茶会では美味しいものを食べつつ、掛け軸に親しむことができるので、堅苦しくなく楽しみながら掛け軸について勉強できるのではないでしょうか。
抹茶やお菓子好きな人にはおすすめの掛け軸の親しみ方です。
日本の伝統文化に触れる機会を作ろう!

日本を訪れる外国人観光客は日本の文化に興味津々です。
「日本の文化を紹介して」と言われた時に少しでも詳しく紹介できたらと思いませんか。
掛け軸は、古くから床の間を美しく飾ってきた日本の伝統文化のひとつです。
外国人観光客からすれば、お寺などで掛け軸を見かけても馴染みがなく、とりわけキャンバス画など洋画の文化である欧米圏の人々には新鮮に感じられるでしょう。
そのような場面に出くわしたら、日本では床の間に季節の花や鳥などの動物などを描いた絵を飾るものだと説明できると喜ばれるでしょう。
日本人なら教養の一つとして親しんでおいて損はありません。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ
より詳しい情報を知りたい方はこちら
骨董品買取をもっと見る