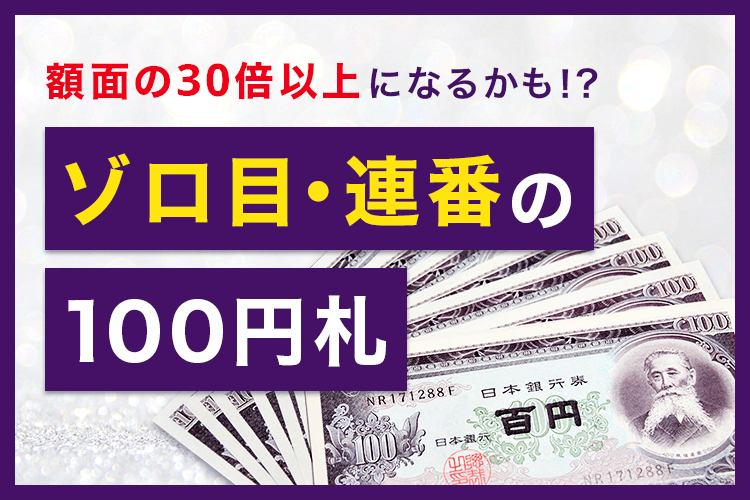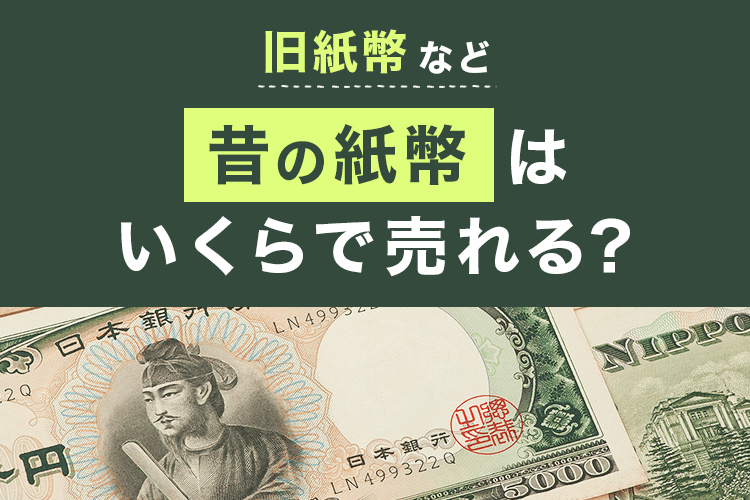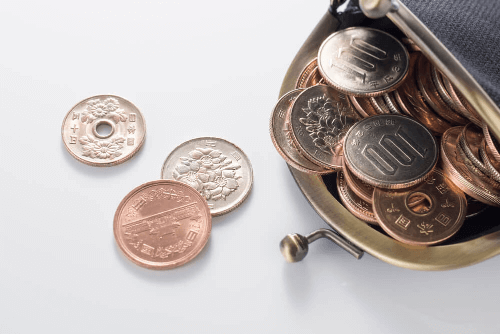旧千円札や旧百円札はいつまで発行されていた? 伊藤博文などのお札の買取価格について紹介
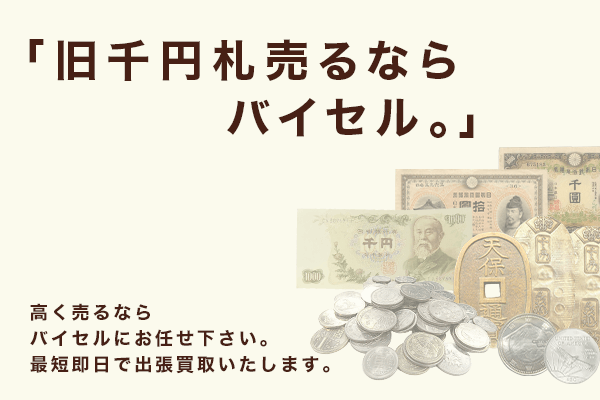
みなさんのご自宅に、旧千円札は眠っていませんか?
古いお札が切り替わるときにとっておいたり、初版のときのものを使わずに持っていたりしている方もいるかもしれません。
今回は、旧千円札について、価値はどのくらいになっているのか、古銭買取できるのかといった点について解説します。
掲載品の買い取りに関するお知らせ
一部掲載品については買い取りが難しい場合がございます。
詳しくはオペレーターまでお問い合わせください。
※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。
目次
旧百円札のおもな種類といつまで発行されていたかについて
かつての日本では、百円もお札として発行されていました。過去に発行されたおもな百円札には、明治通宝百円券、大黒札(旧百円券)、藤原鎌足の百円券などがあります。
ここでは、以下の百円券について詳しくご紹介していきましょう。
明治通宝百円券
明治通宝百円券は、1872年(明治5年)4月に発行された百円札です。表面には鳳凰と龍が描かれ、出納頭の割印と明治通宝の文字が入っています。
裏面には青海波、蜻蛉、千鳥、帆立貝、孔雀が描かれているほか、大蔵卿印、記録頭の割印、そして記番号が印刷されています。
ドイツで製造された明治通宝百円券は1870年(明治3年)10月から、国内で製造された明治通宝百円券は1877年(明治10年)7月から1878年(明治11年)6月までの期間になります。
大黒札(旧百円券)
大黒札(旧百円券)は、1885年(明治18年)9月8日に発行が開始され、1927年(昭和2年)2月に兌換銀行券整理法が制定されてことによって、1939年(昭和14年)3月31日限りで運用停止となりました。
表面には、大黒天が小槌と手袋を手にして米俵に腰かけている姿と、表面中央に日輪と光線状の模様が描かれています。なお、大黒札の図案製作者はイタリア人のエドアルド・キヨッソーネが行ないました。
藤原鎌足の百円券
藤原鎌足の百円券は、1900年(明治33年)12月25日に発行が開始され、大黒札と同様、1927年(昭和2年)2月に兌換銀行券整理法が制定されてことによって、1939年(昭和14年)3月31日限りで運用停止となりました。
表面の輪郭枠の形状がめがねのフレームに見えることからちなんで「めがね鎌足」や「めがね百円」と称されています。また、藤原鎌足の百円券は日本で発行された紙幣のなかで最もサイズが大きいとされる紙幣になります。
詳しい百円札の情報はこちら!
旧千円札の種類といつまで発行されていたかについて
千円札はご存知のとおり日本銀行券の一種です。
過去に発行された千円札は、甲号券、B号券、C号券、D号券、E号券の全5種類となっています。
千円紙幣のみ、五千円や一万円紙幣よりも1割ほど厚い紙を使用しているのが特徴です。
以下では、それぞれの種類の千円札について詳しくご紹介します。
日本武尊が描かれている甲号券とは
甲号券は、1945年(昭和20年)8月17日に発行された千円札です。
表面には日本武尊と建部神社が描かれ、「千圓」と中央に文字が入った千円札で、裏面には彩紋が描かれています。
新円切替により、1946年(昭和21年)3月2日には通用停止され、短期間で失効されました。
製造数が810万枚と少なかっただけでなく、高額券であるがゆえにそのほとんどが回収し尽くされているため現存数は少なくなっています。
日本武尊(やまとたけるのみこと)とは
「古事記」「日本書紀」に記されている伝説の英雄で、景行天皇の双子の皇子として生まれたと記されています。
成長してからは反乱を起こした熊襲を討ち、さらに蝦夷も平定しました。
その後、倭国への帰路の途中で伊吹山の荒ぶる神を倒しに向かいますが、神の怒りにふれ病気となってしまいます。
弱った体のまま帰路を進めますが能褒野で力尽き最期を迎えました。
葬られたあとは、白鳥になって飛び立ったといわれています。
聖徳太子が描かれているB号券とは
1950年(昭和25年)1月7日に発行が開始された千円札で、1965年(昭和40年)1月4日に支払停止となりました。
表面には聖徳太子、裏面には左側に法隆寺夢殿、右側には「NIPPON GINKO」と大きく文字が描かれ、透かしには、日銀と桜花が入っています。
また、現在と同じ記番号形式の「アルファベット1桁〜2桁+数字6桁+アルファベット1桁」となった初めての日本紙幣でもあります。
聖徳太子とは
橘豊日皇子(のちの用明天皇)の子として生まれ、推古天皇の即位に際し摂政となり内政・外交に尽力しました。
人材途用のために「冠位十二階」を制定したほか、日本発の憲法である「十七条憲法」を定めるなど集権的官僚国家の基礎をつくりました。
また、外交面では遣隋使を派遣するなど先進文化の輸入にも力を入れています。
仏教信仰にあつく、その興隆のため、法隆寺や四天王寺も建立しました。
伊藤博文が描かれているC号券とは
表面に伊藤博文、裏面に日本銀行が大きく描かれた千円札で透かしには横顔の伊藤博文が使用されています。
1963年(昭和38年)11月1日に発行が始まり、1986年(昭和61年)1月4日支払停止になるまでに129億6,000万枚発行したため、記番号が一巡しています。
発行開始から記番号が褐色に変更され、マイクロ文字という微小な文字を線や図柄の一部に入れ込む技術を採用し特殊発光インクを使用することで偽造防止されています。
伊藤博文とは
長州藩出身の政治家で初代内閣総理大臣。
吉田松陰の松下村塾に入塾し高杉晋作らと学んだあと、長州藩の留学生として、イギリスに留学し英語を学びました。
明治新政府においても英語力を評価され外国事務掛に就き、30歳のときに岩倉使節団の副使としてヨーロッパ各国の憲法を調べるため、欧米諸国を視察しました。
1885年(明治18年)には、日本に初めて内閣制度を導入し初代内閣総理大臣となります。
翌年には憲法草案起草に着手し、1889年(明治22年)2月に大日本帝国憲法を発布しました。
大隈、板垣を後継に推し、日本最初の政党内閣(第1次大隈憲政党内閣)も実現。
第2次日韓協約締結にあたり韓国統監に就任しましたが、統監辞任後、ハルビン駅頭で韓国の民族運動家安重根に狙撃され死去しました。
夏目漱石が描かれているD号券とは
1984年(昭和59年)11月1日に発行が開始され、2007年(平成19年)4月2日に支払停止になるまでに、129億6千万枚も発行された紙幣です。
膨大な発行枚数によって記番号が一巡していたため、2000年(平成12年)4月3日発行分から暗緑色に記番号が変更されました。
D号券から、肖像に文化人が採用されており、千円券には夏目漱石が選ばれています。
また、ほかにも、視覚障害者が触って券種を判断できるように識別マークが施されているのも特徴の紙幣です。
夏目漱石とは
近代日本の代表的な小説家、英文学者。
現在の東京大学英文学科を卒業後、松山中学校教師、第五高等学校教授、イギリス留学を経て、第一高等学校、東大の教壇に立った。
「ホトトギス」に発表した『吾輩は猫である』『坊ちゃん』などで文名を上げた。
その他の代表作には、『三四郎』『それから』『草枕』『こころ』『明暗』などがあります。
野口英世が描かれているE号券とは
表面に野口英世、裏面には逆さ富士(本栖湖からの富士山の眺め)と桜が描かれている千円札で、逆さ富士は「湖畔の春」という岡田紅陽の写真をもとに描かれました。
2004年(平成16年)11月1日発行開始され、D二千円券に採用された深凹版印刷、潜像模様、パールインク、ユーリオンという偽造防止技術が使われています。
また、新しく採用された偽造防止技術として、表面右側に「すき入れバーパターン」と呼ばれる、用紙を薄くしてすきを入れる方法が用いられています。
表面と裏面に「二」「ホ」「ン」の文字がシークレットマークとして入れられています。記番号の組み合わせが少なくなってきたことをきっかけに、2011年(平成23年)7月19日より記番号の色を黒色から褐色へと変更しました。
野口英世とは
福島県翁島村(現:猪苗代町)に生まれの細菌学者。
1歳半のときに左手に大やけどを負い、2度の手術を受けます。
左手は完全に自由になったわけではありませんでしたが、医学のすばらしさを知った経験から医者を志します。
ほぼ独学で勉強をし、20歳の若さで医師免許を取得。
伝染病研究所に入所したあと、1900年渡米しロックフェラー医学研究所助手となります。
1911年にはスピロヘータ純粋培養に成功して世界的名声を得ます。
狂犬病・痘瘡・小児麻痺の研究でも業績を挙げましたが、アフリカに渡ったのち、黄熱病病原体の研究中に感染し死去しました。
旧百円札や旧千円札の買取相場
ここまでで旧百円札や旧千円札についての理解が深まったと思います。
それでは実際の旧百円札や旧千円札の買取相場について解説していきます。
旧百円札の買取相場
旧百円札には高値で取引されるお札が多く存在します。
明治通宝百円券
明治通宝百円券は発行枚数が24,000枚余りと極めて流通数が少ないため、高額な価値が見込めます。
しかも、現存数は10枚に満たないと予想されているため、希少価値が極めて高く市場に出回ることはほぼありません。
もし買取市場に出回れば数万円程度で取引される可能性があります。
大黒札
大黒札は希少性が高く実際の売買事例があまりないのですが、美品であれば数千円程度になることもある百円札です。
黒札は百円札以外に十円札や一円札も発行されていますが、同じく希少価値の高い十円札だと、状態によっては高額で取引されています。
藤原鎌足の百円券
明治24年に発行された「めがね百円」といわれる、藤原鎌足が描かれた百円券です。
「改造百円券」と「甲号券」の2種類が存在し、保存状態が良い前期甲号券は数百万円以上で取引されることもあります。
明治33年に発行された藤原鎌足百円券(甲号)は通し番号が万葉記号のタイプとアラビア記号のタイプがあり、発行時期や種類によって価値に差が出ます。
旧千円札の買取相場
旧千円札のなかには数万円、数十万円も価値のあるお札が存在します。
甲号券(日本武尊)
日本初の千円札である甲号券は流通量が少ない紙幣です。
当時の千円は極めて高額な紙幣だったので実際に使用される機会が少なかったからです。
高額紙幣ゆえに、その大半が回収されているため、美品や未使用の場合には高額で取引されます。
B号券(聖徳太子)
B号券は「アルファベット+数字+アルファベット」の並びで記載された初の紙幣です。
ただし、現在も有効な紙幣になるので基本的には額面ベースでの価値になりますが、エラープリントやミスプリントの場合には価値が跳ねあがります。
C号券(伊藤博文)
C号券は額面どおりの千円前後で取引されています。
C号券は記号の色で前期と後期、アルファベット2桁と1桁の組み合わせで4種類に分別されます。
こちらも現行の紙幣になるため基本的には額面どおりの価値ですが、未使用や希少な紙幣ナンバーの場合には高額で取引されています。
D号券(夏目漱石)
夏目漱石が描かれているD号券も現在も使用できる紙幣になります。
発行枚数も多いため額面どおりの価値で取引されることもあります。
ただし、エラープリントやゾロ目、キリ番など希少性が高い紙幣の場合、高値で取引されることもあります。
E号券(野口英世)
E号券も額面どおりの価値で取引される傾向にあります。
金融機関で未使用品も容易に手に入るので額面以上の価値はありません。
D号券と同様にエラープリントやゾロ目などでなければ額面以上で取引されることはないでしょう。
旧百円札や旧千円札はいまでも使えるのか?
紙幣やお札は、一度国から発行されると、法律に基づく特別な措置がとられない限り、ずっと使い続けられるものとなります。
したがって、現在においては、以下の旧百円札と旧千円札がスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店でも使えるようになっています。
【旧百円札】
- A百円券(聖徳太子)
- B百円券(板垣退助)
【旧千円札】
- B千円券(聖徳太子)
- C千円券(伊藤博文)
- D千円券(夏目漱石)
これらの旧百円札や旧千円札は、以下のような金融機関で現行の同一金種に交換することも可能です。
例えば、旧百円札一枚を銀行に持ち込めば、百円玉一枚と交換できることになります。
- 日本銀行
- 地方銀行
- 信用金庫
旧紙幣の交換には、1つ注意点があります。
それは、郵便局の場合、両替商としての登録がないため、旧紙幣の交換は行なえないことです。
したがって、旧紙幣を現行のお金に交換するときには、必ず銀行か信用金庫に持ち込むようにしてください。
なお、同一金種への交換という形で金融機関に戻ってきた旧紙幣は、廃棄処分されます。
交換した旧紙幣が再び流通することはありません。
古銭買取における旧百円札の買い取りはどれくらいの価値がある?
明治から昭和にかけて普及されていた旧百円札ですが、現在でも現行紙幣として使うことができます。
およそ120年経った現代では、どれくらいの価値があるのでしょうか。
発行数は少ないため、もしかすると予想以上の値がつくかもしれません。
以下では、額面以上の買い取りを狙うことが可能になるパターンを紹介します。
未使用かつきれいな状態であること
一度も使用されていない状態であれば、コレクター価値も上がるため、額面以上での買い取りも可能になるかもしれません。
旧百円札で未使用の状態はかなり希少性が高いので、高値がつく可能性があります。
現存数と取引数
旧百円札の現存数は非常に少なく、それに比例して取引数も非常に少なくなっています。
基本的に市場流通はしていないので、ご自宅に眠っているケースや収集家の方が保存しているもの程度しかない状態です。
もし、引越しや家の整理をしているときなどで、旧百円札が出てきたら一度査定に出してみてもよいでしょう。
エラープリント
旧百円札に多いとされているエラープリントは、印刷ズレや数字ズレ、耳つきがある状態のお札を指します。
エラープリントの度合いが大きければ大きいほど、高値がつきやすくなります。
紙幣番号の組み合わせと配列
紙幣番号がゾロ目か、数字部分が1番の紙幣はプレミアがつきやすくなります。
また、キリ番や数字が階段のようにきれいに並んでいる場合も紙幣価値が上がる可能性が高いです。
古銭買取における旧千円札の買い取りはどれくらいの価値がある?

B号券の聖徳太子、C号券の伊藤博文、D号券の夏目漱石を絵柄とした旧千円札は、現在も使用できる有効券となっています。
枚数も多いため一部例外を除き基本的には額面を下回る買取価格になってしまうのが現状です。
以下では額面以上の買い取りを狙うことが可能になる「例外パターン」を紹介します。
未使用かつきれいな状態であること
一度も使用されていない状態であればコレクター価値も上がるため額面以上での買い取りも可能になるかもしれません。
発行番号が若い番号であること
前期に発行された千円札に価値があるといわれています。
前期と後期かの見分け方としては、番号や紙の色などが挙げられます。
アルファベット1桁であること
発行番号と同様に、前期に発行された千円札に価値があるといわれています。
前期と後期かの見分けるポイントは、やはり番号や紙の色などです。
記番号に使用されたインクが黒色であること
記番号に使用されたインクは前期と後期で異なり、黒のインクが使用されているのは前期になります。
珍番号であること
「A123456B」のようにアルファベットが1桁のものや数字が並んでいるもの、「CD888888E」のようにゾロ目になっているものなどが挙げられます。
サンドイッチ番号であること
「B○○○○○○B」のように、最初のアルファベット1桁と最後のアルファベットが同じであったり、「811118」のように、6桁の数字の両端が同じ数字で、挟まれた4桁の数字が同じだったりをコレクターの間ではサンドイッチと呼びます。
エラープリント
印刷がずれている、裏面にも表の絵柄が印刷されている、上下が逆さまにプリントされているなど、印刷ミスがある状態を指します。エラープリントの度合いが、大きければ大きいほど高値がつくのが特徴です。

より詳しい情報を知りたい方はこちら
古銭買取をもっと見る
旧百円札や旧千円札を買い取りに出す際のポイント
手元に旧百円札や旧千円札があり買い取りに出す場合、注意しなければいけない点があります。買取価格を少しでも上げる方法をご紹介しますので、参考にしてみてください。
汚れがあってもクリーニングをしない
旧紙幣を集めているコレクターには、紙幣の古さに価値を感じている方が多いため、あえてきれいにせずそのままで出すことがプラス査定を導くポイントになります。
紙幣に汚れなどが残っていることで、価値は上がっていくこともあります。
また、下手にクリーニングを行なうことで、紙幣の状態を悪くしてしまう可能性もあります。
そのため、紙幣を買取店に出すときには、クリーニングせずにそのまま査定してもらうようにしましょう。
鑑定書も査定時に持ち込む
鑑定書とは、専門家の鑑定によって出た結果を記したものです。
あらかじめ査定士に鑑定されていることを証明できていれば、高値で買い取ってもらいやすくなります。
鑑定書をお持ちの方は、買取査定を希望する紙幣と一緒に買取店へ持参しましょう。
おわりに
B号券の聖徳太子、C号券の伊藤博文、D号券の夏目漱石を絵柄とした旧千円札は、そのまま使用可能です。
また、大量に発行されていますので、千円以上の価値を見込むのは難しい旧千円となります。
しかし、そのなかでも、通し番号が珍しい「珍番号」の旧千円札やエラープリントになっている旧千円札は、価値を上げることが可能です。
美品で未使用ならば、さらに価値が上がるかもしれません。
使わずに保管中の旧千円札をお持ちでしたら、番号や絵柄などを隅々まで確認してみるのも良いかもしれません。
そうすることで、これまで見向きもしなかった旧紙幣に思わぬ価値がつく可能性もあるのではないでしょうか。
こんなコラムも読まれています

より詳しい情報を知りたい方はこちら
古銭買取をもっと見る