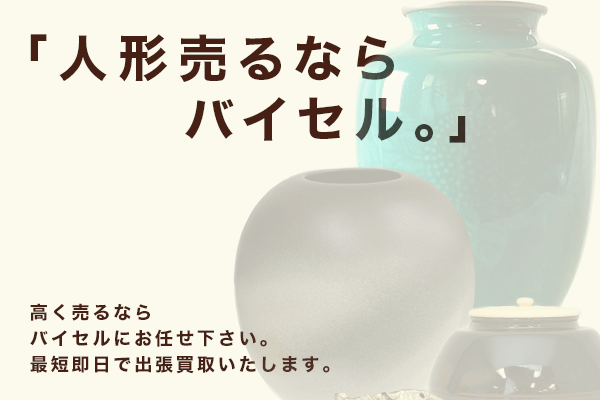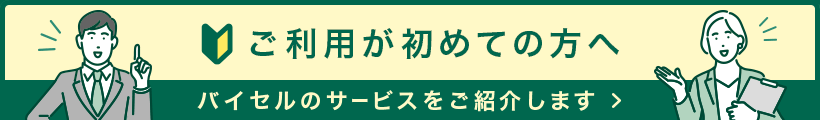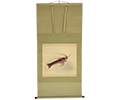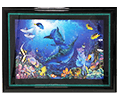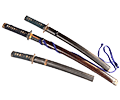秋山信子の人形は価値が高い?人気作品や高価買取のポイントを解説

秋山信子(あきやまのぶこ)は、重要無形文化財「衣裳人形」の保持者として人間国宝に認定されている日本の人形作家です。
単に愛らしいだけでなく、人物の内面的な深さと芯の強さ、そして題材となった土地の文化や自然の奥深さまで感じさせる表現は非常に高く評価されています。
骨董品買取市場での取引例は多くありませんが、作品のクオリティと人気から非常に高い価値があることは間違いありません。
本記事では、秋山信子作品の特徴や代表作・有名作品に加えて、秋山信子作品の価値と人気になりやすい人形の特徴、秋山信子の人形を高価買取してもらうためのポイントなどについてご紹介します。
掲載品の買い取りに関するお知らせ
一部掲載品については買い取りが難しい場合がございます。
詳しくはオペレーターまでお問い合わせください。
※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。


「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!
秋山信子とは
秋山信子(1928-2024)は、重要無形文化財「衣裳人形」の保持者として人間国宝に認定されている日本の人形作家です。
大阪府大阪市に生まれた秋山信子は、幼い頃から病弱であったため屋外よりも室内で過ごすことが多かったといいます。
そして、通院していた病院の待合室に偶然飾ってあった手作り人形に魅せられたことが、人形作りを始めるきっかけとなりました。
1955年、27歳で京都で活躍していた人形作家の大林蘇乃(おおばやしその 1910-1971)に師事し、桐塑(とうそ:桐のおがくずと糊を混ぜて練り上げた、人形制作に用いられる粘土状の素材)・和紙貼(素材の表面に和紙を貼り付ける技法)・木目込(きめこみ:桐塑などの人形の本体に筋彫りを入れ、そこに布の端を押し込む人形に布をまとわせる技法)などの伝統的な人形制作技法を学びました。
すると1959年には近畿支部第1回日本伝統工芸展で初入選、全日本女流人形展で受賞を果たすなど、新進気鋭の人形作家として知られるようになります。
その後も数々の工芸展や人形展で活躍した秋山信子は日本伝統工芸展の審査員を務めるようになり、いち作家の枠を超えて日本の伝統工芸に貢献していきます。
1990年代に入ると長年の功績が認められ、1990年には紫綬褒章を受賞、1996年には重要無形文化財「衣裳人形」の保持者に認定され、1998年には勲四等宝冠章を受章しました。
秋山信子が手掛ける衣装人形とは
「衣装人形」とは、衣装(着物などの布)を着せ付けた鑑賞用の人形のことです。
日本人形の中でも、雛人形・五月人形・市松人形などを除いた、主に風俗や人物の姿を表現するために衣装を着せ付けた鑑賞用の人形を指します。
「風俗人形」や「浮世人形」とも呼ばれます。
胴体は、木や藁を芯として形が作られることが多く、頭や手足は桐塑や木彫りなどで作られることが多いです。
仕立てられた布製の衣装を胴体に実際に着せ付け、頭部や手足に胡粉(ごふん:貝殻を砕いた白い顔料)を塗り重ねて肌の質感を出し、彩色や髪付けを行います。
そして手足の角度や衣のしわを整え、人形に躍動感や表情を与える、といったような手順で制作されます。
「着物を着ているように見せる」のではなくて、仕立てた着物を胴体に実際に着せ付けるのが衣装人形の特徴で、豪華で立体的な衣装の重ねやしわが表現できます。
秋山信子の作風
秋山信子の人形作りのベースとなるのが桐塑です。
木彫りの骨組みに桐塑で肉付けして形を整えることで、人形に微妙な表情や動きを持たせ、完成度の高い造形感覚を表現できます。
そこに和紙や布を貼り付け、彩色し、漆を塗り、木目込みを行うなど複数の技法を組み合わせて、人形の質感を表現します。
衣装を着せる際には、モデルにポーズをとらせることで体の線に伴ってできる衣装の細かい襞を研究し、写実的に表現しています。
人形の衣装には、伝統的な着物などに使われる布が用いられます。
秋山信子の人形の題材としては、
- 地元の大阪の祭りや日本の各地に伝わる祭礼行事など伝統文化や風俗をテーマにしたもの
- 沖縄、アイヌ、韓国・中国の少数民族など、さまざまな民族の伝統文化や人々をテーマにしたもの
が多いです。
秋山信子の人形は単に愛らしいだけでなく、その中に人物の内面的な深さと芯の強さ、そしてその土地の文化や自然の奥深さなどを感じさせます。
秋山信子の人形は価値が高い?人気になりやすい作品の特徴とは
人間国宝であり、紫綬褒章・勲四等宝冠章の受章者でもある秋山信子の作品には美術館に所蔵されているものも多く、非常に高く評価されています。
骨董品として買取市場で売買されるとすれば、その価値は非常に高いと言えるでしょう。
秋山信子作品の中でも特に価値が高いとされているのは、人間国宝認定後などの円熟期の作品です。
特に、制作に多大な時間と手間がかかるような大作は価値が高くなりやすいでしょう。
※バイセルでは日本人形の買取が難しい場合がございます。
※お持ちの人形が買取可能かどうかについて、詳しくはオペレーターまでお問い合わせください。
日本人形のほかビスクドールやフィギュリンといった人形の買取情報や、そのほか骨董品の買取相場、バイセルでの買取実績については以下の各ページをご参照ください。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ秋山信子の代表作
桐塑や木目込みなどの伝統技法を使いながら、人物の内面的な深さや芯の強さを表現する秋山信子の衣装人形は、多くの美術ファン・工芸ファンを魅了しています。
ここでは、秋山信子の衣装人形の中でも特に人気の高い、代表作と言うべき作品についてご紹介します。
潮騒
秋山信子の「潮騒」(1960)は、同年に開催された第7回日本伝統工芸展に初めて出品し、見事に初入選を果たした作品です。
さらに大阪府教育委員会賞を受賞しており、秋山信子が伝統工芸の世界で認められる大きなきっかけとなった初期の代表作と言えます。
「潮騒」は、秋山信子が体を悪くして休養していた際に偶然読んだ、沖縄の詩人の歌に詠まれた沖縄の自然に感動したことが制作のきっかけであったといいます。
沖縄の自然の中にたたずむ人物をかたどることによって、自然の豊かさやそこに暮らす人々の温かい心までがにじみ出るような情感が出ています。
秋山信子はのちに沖縄の風俗を題材とする作品を多く作っていますが、「潮騒」は沖縄への関心と敬意を示す原点と言えるでしょう。
命名
秋山信子の「命名」(1980)は、同年の第27回日本伝統工芸展に出品された後、文化庁によって買い上げられた作品です。
国の機関に所蔵されることは、作品の美術的・文化的価値が高いことを示しています。
現在は、石川県の国立工芸館に収蔵されています。
「命名」は、生まれたばかりの赤ちゃんを抱く女性の姿をかたどった人形となっています。
母親の衣装や赤ちゃんを包む布が繊細に表現されています。
母親の表情からは、生命が誕生した喜びと家族の深い愛情が感じられます。
浜下り(はまうり)
秋山信子の「浜下り」(2000)は、第47回日本伝統工芸展に出品された後、文化庁に買い上げられた作品です。
やはり国の機関の所蔵となったことは、美術工芸品としての高い評価を示しています。
現在は東京都の文化庁分室に所蔵されています 浜下りとは沖縄の八重山地方などで旧暦3月3日に行われる伝統的な行事で、女性たちが浜辺で歌や踊りに興じ、豊穣を祈願するものです。
別名「女の祭り」とも呼ばれ、「浜下り」の題材になっているのはこの祭りに参加している女性です。
人形の衣裳には藍染の布を木目込んだり、銀砂子(ぎんすなご:銀箔を細かい粉にしたもの)を散らすなどの工夫が凝らされ、青々とした海の雰囲気や浜辺の情景が見事に表現されています。
沖縄の風土に根ざした人々の暮らしや精神性を描き出した、情感豊かな作品です。
群星(むりかぶし)
「群星」(2008)は、秋山信子が沖縄の風俗を描いたものの中でも円熟期の名作として知られる作品です。
「むりかぶし」は沖縄の八重山地方などで使われる言葉で、「すばる(プレアデス星団)」を意味します。
「群星」の題材となっているのは、無数の星がきらめく夜空を見上げる人物です。
沖縄の悠久の自然とそこに輝く星空、そしてそこに生きる人々の静かで力強い精神性が表現されています。
夜空を見上げ、星に思いを馳せる人物の姿を通して、詩的で幻想的な世界を感じられます。
ほかにも「大月」「里神楽」「豊穣」「西代神楽」「十五夜の獅子加那志」「鳴沙山夕照 望郷」「月下」「小春日和」など、人間国宝である秋山信子には数多くの人気作品・有名作品があります。
また、ここに名前のない作品であっても、秋山信子作品であれば保存状態などの条件によって買取してもらえる可能性があります。
※バイセルでは日本人形の買取が難しい場合がございます。
※お持ちの人形が買取可能かどうかについて、詳しくはオペレーターまでお問い合わせください。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ秋山信子の人形を高価買取してもらうためのポイント
人間国宝であり、紫綬褒章・勲四等宝冠章の受章者でもある秋山信子の人形は、当然ながら、美術界・工芸会で絶大な支持を得ています。
では、そんな秋山信子の人形を少しでも高く売るためには、どのようなポイントに気をつければ良いでしょうか。
秋山信子作品を含む人形の買取において、より高く買取してもらうために知っておきたい3つのポイントをご紹介します。
- 綺麗な状態で保存しておく
- 共箱や付属書類などの付属品を揃えておく
- 入手経路などの来歴を明確にしておく
綺麗な状態で保存しておく
人形の買取で、買取価格に大きく関わるのが「保存状態」です。
保存状態の良いもの(制作当時の状態をなるべく保っているもの)は、買取価格が高くなりやすいでしょう。
その一方で、日焼けがある、衣装や人形の体にカビが発生しているなど、作品の状態が悪ければその分だけ価値は下がってしまいます。
そうならないためにも、直射日光を避ける、風通しの良い場所で保管する、除湿剤を使うなど、人形の状態を保つための工夫をしてあげることが重要です。
共箱や付属書類などの付属品を揃えておく
人形を含む骨董品の買取では、共箱などの付属品の有無も買取価格に大きく関わってきます。
共箱とは作品を収めるための木箱のことで、作者の箱書きが入っている場合もあります。
そのため、共箱は重要なコレクションの一部であると同時に、本物の証明になってくれるため非常に重要なのです。
秋山信子作品の場合、共箱に制作年月・「秋山信子作」の署名・朱色の印章といった箱書きが入っていることがあります。
このような箱書きがあることで買取市場での信頼性が増し、より高い需要を集めて買取価格が高くなる可能性があります。
人形の付属書類としては、説明書・保証書・由来書などがあります。
また、人形の着替えや飾りが付属している場合もあります。
これらの付属品も、人形本体とともに大切に保管しておいてください。
入手経路などの来歴を明確にしておく
秋山信子の人形など価値ある骨董品の査定では、買取市場における作品の信頼性のために「どこで手に入れたか」「いつ購入したか」「誰から譲り受けたか」など購入に至るまでの背景が確認されます。
例えば「業界で信頼されている専門店で購入した」「著名なコレクターから譲り受けた」などの来歴は、作品の価値を判断するうえでも重要な情報になります。
そして、その来歴を証明する書類等があればさらに信憑性が増し、買取市場における信用度が増すことでより高く売れるかもしれません。
入手した経路や時期、過去に所有していた人物といった記録がある場合には、処分せずに大切に保管しておきましょう。

より詳しい情報を知りたい方はこちら
骨董品買取をもっと見る
こんなコラムも読まれています
- 会田誠の絵画の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- エマニュエル・ヴィラニスのブロンズ像の買取相場は?高価買取のポイントも解説
- 愛新覚羅溥傑の書や掛け軸の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 荻須高徳作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 秋野不矩作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 池上秀畝作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 岡鹿之助作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 岡田三郎助作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 大山忠作作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 小川芋銭作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説