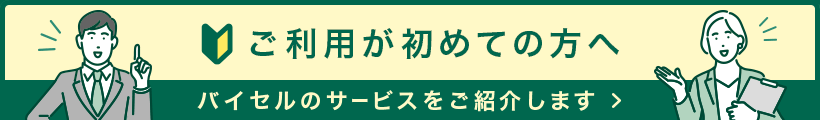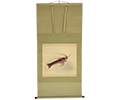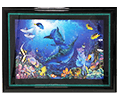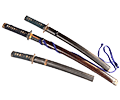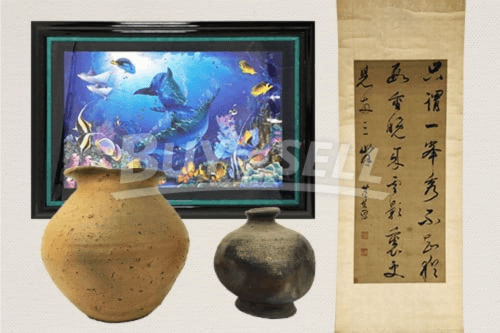王鐸の書や掛け軸の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説

王鐸(おうたく)は、力強く躍動感あふれる草書・行書などの書体で有名な中国の書家です。
官としても優れていたことから歴史上の重要人物でもあり、その作品は中国美術の愛好家を中心に高い評価を得ています。
骨董品買取市場でも王鐸の書や掛け軸は非常に人気が高く、高価買取されるケースも少なくありません。
本記事では、王鐸の人物像や書の特徴、代表作に加えて、買取市場で高く売れる理由、高く売れやすい王鐸作品の特徴、王鐸の書や掛け軸を高価買取してもらうためのポイントなどについてご紹介します。
※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。


「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!
王鐸とは
王鐸(1592-1652)は、中国の明朝末期から清朝初期の時代に活躍した書家です。
また、官としても非常に優秀で、明朝末期には礼部尚書(現代日本でいうところの文部科学大臣に相当する位)にも任命されました。
背が高く、立派な長い髯をたくわえており、いかにも中国の高官らしい風貌であったとされています。
王鐸は、現在の中国・河南省に生まれました。
幼い頃から書はもちろん、詩作や絵画、学問においても非凡な才能を示しましたが、本人が最も強い関心を持ったのが書であったといいます。
13歳の頃から、東晋時代(317~420年)の書家たちの作品をまとめた『集王聖教序』という書物を書き写すなどして、書の道を歩み始めたようです。
30歳で科挙に合格して官僚になると出世を重ね、1644年には礼部尚書に任命されます。
その直後に明王朝が清に降伏して倒れてしまうのですが、官としても書家としても優秀であった王鐸は清王朝にも手厚く迎えられます。
清王朝で明史の編纂の仕事をしながら、書家としては伝統に根ざしつつもオリジナリティある、独自の書体の開発に努めました。
そんな王鐸の作品は中国の書道史において、伝統を継承しつつも革新をもたらした重要な存在として高く評価されています。
書家・王鐸の作風
王鐸は「行草の神」と称されるほど、力強く躍動感あふれる草書と行書を得意としました。
二王(におう)と呼ばれる東晋時代の2人の書家、王羲之(おうぎし 303-361)と王献之(おうけんし 344-386)の書を深く学び、筆を勢いよく動かす「連綿草(れんめんそう:複数の文字を一気に続けて書く草書)」や、太い線と細い線を織り交ぜる「一字連綿」の技法を確立しました。
王鐸の作品は、筆に墨をたっぷり含ませ、太く力強い線を描くのが1つの特徴です。
また、字の大きさに変化をつけ、行間を大胆に空けることで、作品全体に動きと奥行きを与えています。
墨の濃淡やかすれも巧みに使い、墨象(ぼくしょう:墨の造形美)的な美しさを追及している点も特徴と言えます。
その迫力とリズム感が王鐸作品の魅力になっており、掛け軸などの形で親しまれています。
そして、王鐸は文章の意味よりも、書くことそのもの、書くことへの情熱にこだわりました。
王鐸は、臨書(過去の書家の作品と同じ字を書く)を多数残していますが、多くの臨書ではもとの作品とはまったく異なる独自の書体を用いており、脱字も多く見られます。
そこには、文章の意味よりも、書くことそのものへの喜びが感じられます。
そこから生み出されるダイナミックさは王鐸作品の大きな魅力となっており、高い人気を集めています。
王鐸の書以外の作品
王鐸は書のほかに詩や絵画などの作品も残しています。
自ら創作した詩を、書の題材とすることもあります。
絵画では、墨で描いた山水画が特に有名です。
王鐸作品の買取価格は高い?高く売れやすいポイントとは
ダイナミックな独自の書体で書かれる王鐸の書や掛け軸には、歴史的価値もあいまって高い評価を受けている作品も多いです。
骨董品買取市場でも人気は非常に高く、高価買取されるケースもあるでしょう。
王鐸作品の中でも高く買取されやすいのは、王鐸の肉筆による書作品です。
特に、王鐸の代名詞である「行草」による、ダイナミックな筆遣いが存分に発揮された作品には高い価値がつきやすいでしょう。
王鐸だけでなく、書や掛け軸など美術品の買取では有名作家の作品ほど買取相場が高くなりやすい傾向があります。
以下のページでは、有名作家の作品など書や掛け軸の買取相場、書や掛け軸を高く売るためのポイントといった買取情報について記載してございます。
また、バイセルでの書や掛け軸の買取実績についても記載してございます。
参考までにぜひご参照ください。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ王鐸の代表作
ダイナミックな迫力ある書が人気の王鐸ですが、代表作と言えるような人気作品にはどのようなものがあるでしょうか。
王鐸作品の中でも特に評価の高いものとして、以下の3つをご紹介します。
詩巻
王鐸の「詩巻」はその名の通り、詩文を書いた書作品です。
有名なものとしては、自作の五言律詩を草書で書いて友人に贈った「贈張抱一草書詩巻(ぞうちょうほういちそうしょしかん)」(東京国立博物館所蔵)や、杜甫(とほ 712-770)の詩を臨書した「杜律詩巻」などがあります。
特に七言律詩などは文字数が多いこともあり、連綿草の技法が用いられていることが多いです。
これにより、作品全体に途切れることのない力強いリズムと、速度感のある流れが生まれています。
また、墨の濃淡やかすれが意図的に使い分けられており、潤いのある線とかすれた線が混在することで、筆の勢いがより強く感じられます。
字の大小や傾きも大胆に変化しており、それが見る者に飽きさせないダイナミックさを生み出しています。
臨褚遂良尺牘
「臨褚遂良尺牘(りんちょすいりょうせきとう)は、「一日臨書し、一日創作する」と公言するほど生涯にわたって臨書を続けた王鐸の臨書作品の中でも、傑作と言われる作品の1つです。
唐時代の書家・褚遂良(ちょすいりょう 596-658)の書を臨書した作品で、王鐸の卓越した技量と独自の解釈が凝縮されています。
「尺牘」とは手紙のことです。
この作品では、褚遂良が書いた手紙の書風を学んだうえで王鐸の感性や書風を大胆に取り入れ、原帖とは異なる新たな芸術性を生み出しています。
王鐸の得意とする力強い連綿草が特徴で、原帖の字形や構成を尊重しながらも、字の大小や行間の余白を大胆に変化させており、王鐸らしいリズム感があります。
また、墨の濃淡やかすれの表現が巧みで、線の豊かな変化によって作品に奥行きと躍動感が生まれています。
擬山園帖
「擬山園帖(ぎざんえんじょう)」は、王鐸の書を彼の息子である王無咎(おうむきゅう)が中心となって刻した法帖(ほうじょう:書蹟を保存し、鑑賞・学書用に供するためにまとめたもの)です。
いわゆる王鐸作品とは少し違いますが、後世に王鐸の書風を伝える貴重な手本として作成されました。
「擬山園帖」の内容としては、多くが王鐸が臨書した作品で構成されています。
特に、王鐸が若いころから深く学んだ二王(王羲之・王献之)や、唐・宋時代の有名書家の臨書が多いです。
この「擬山園帖」を通じて、王鐸の臨書における独創的な解釈や、彼独自の連綿草、線の太細や墨の潤渇といった特徴を体系的に見ることができます。
特に、原帖と見比べることで、王鐸ならではの大胆な構成、力強い筆致が顕著に表れます。
「擬山園帖」は王鐸の書風の真髄を伝える重要な資料であり、多くの書道愛好家や研究者にとって、彼の書を理解する上で不可欠な存在となっています。
「擬山園帖」によって彼の書風がより広く知られるようになり、多くの書家が手本としました。
このほかにも、「琅華館帖(ろうかかんじょう)」「臨王献之豹奴帖軸(りんおうけんしひょうどじょうじく)」「臨王羲之鵞群帖軸(りんおうぎしがぐんじょうじく)」「淳化閣帖(じゅんかかくじょう)」など、王鐸の有名作品は数多くあります。
また、王鐸の作品なら、ここに挙げたものでなくても保存状態などの条件によって高く買取される場合があります。
お持ちの王鐸作品の具体的な価値については、ぜひ1度バイセルの無料査定でお確かめください。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ王鐸の書や掛け軸を高価買取してもらうためのポイント
王鐸の書や掛け軸は、ダイナミックで迫力ある独自の書体の人気や歴史的な価値などから買取市場でも高く評価されています。
では、王鐸の書や掛け軸を少しでも高く売るためには、どのようなポイントに気をつければ良いでしょうか。
王鐸作品を含む書や掛け軸の買取において、より高く買取してもらうために知っておきたい3つのポイントをご紹介します。
- 綺麗な状態で保存しておく
- 箱や鑑定書などの付属品を揃えておく
- 入手経路などの来歴を明確にしておく
綺麗な状態で保存しておく
書や掛け軸の買取で、買取価格に大きく関わるのが「保存状態」です。
保存状態の良いもの(制作当時の状態をなるべく保っているもの)は、買取価格が高くなりやすいでしょう。
その一方で、日焼け・シワ・色あせ・虫食いがあるなど、作品の状態が悪ければその分だけ価値は下がってしまいます。
そうならないためにも、直射日光を避ける、飾らない場合は箱に入れて風通しの良い場所で保管するなど、書や掛け軸の状態を保つための工夫をしてあげることが重要です。
箱や鑑定書などの付属品を揃えておく
書や掛け軸を含む骨董品の買取では、箱などの付属品の有無も買取価格に大きく関わってきます。
箱などの付属品は重要なコレクションの一部であると同時に、作者の箱書きがあるなど、本物の証明になってくれることもあります。
そのため、付属品があることで買取市場での信頼性が増し、より高い需要を集めて買取価格が高くなる可能性があるのです。
書や掛け軸の付属品としては、箱、風鎮(ふうちん:掛け軸の下部に吊り下げる重り)や紐(掛け軸を巻く際や吊るす際に使う)、鑑定書などの付属資料があります。
箱や風鎮・紐などの付属品は、汚れていたとしても揃っているだけで買取価格に影響するため、処分せずにとっておきましょう。
また、鑑定書がある場合はやはり買取市場における信頼性につながって買取価格アップにつながる可能性があります。
書や掛け軸本体とともに大切に保管しておいてください。
入手経路などの来歴を明確にしておく
王鐸の書・掛け軸など価値ある骨董品の査定では、買取市場における作品の信頼性のために「どこで手に入れたか」「いつ購入したか」「誰から譲り受けたか」など購入に至るまでの背景が確認されます。
例えば「業界で信頼されている専門店で購入した」「著名な好事家が所有していた」などの来歴は、作品の価値を判断するうえでも重要な情報になります。
そして、その来歴を証明する書類等があればさらに信憑性が増し、買取市場における信用度が増すことでより高く売れるかもしれません。
入手した経路や時期、過去に所有していた人物といった記録がある場合には、処分せずに大切に保管しておきましょう。
王鐸作品を売るなら買取実績豊富なバイセルへ
王鐸の書や掛け軸の買取をお考えなら、骨董品買取のバイセルにお任せください。
バイセルは日本全国で骨董品・美術品などの買取サービスをご提供し、たくさんのお客様・リピーター様からご指名をいただいてまいりました。
バイセルの査定士は、高い専門知識と豊富な査定経験を生かして、書や掛け軸1点1点の価値をしっかりと見極め、正確に鑑定します。
バイセルの出張買取ならお電話1本、手数料完全無料で日本全国への出張買取に対応しております。
「試しに価値がどれくらいか聞いてみたい」「傷や汚れがあって売れるか不安」といった場合にも無料でご相談いただけます。
ぜひ1度お気軽にお試しください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら
骨董品買取をもっと見る
こんなコラムも読まれています
- 書画や掛け軸を高価買取してもらうには?高く売れる作家や買取のコツを紹介!
- 中国の掛け軸ってどんなもの?中国掛け軸の特徴や作家を紹介
- 中国骨董品の代表的な種類8選!価値が高い理由や本物の見分け方を解説
- 中国美術の買取相場は?人気の種類や高く売れる作品の特徴を解説
- 中国骨董の人気ジャンルとその歴史・魅力を解説!価値の見極め方は?
- 中国陶器の価値とは?歴史や時代別の特徴、有名な種類、高価買取のポイントを解説
- 呉昌碩作品の買取価格は高い?掛け軸・書・篆刻の代表作や高く売れる特徴を解説
- 斉白石作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 愛新覚羅溥傑の書や掛け軸の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 愛新覚羅溥儀作品 買取|高く売るために押さえておきたいポイントを解説