海外の有名な現代アート作家15人!世界的な日本人アーティスト19人も紹介
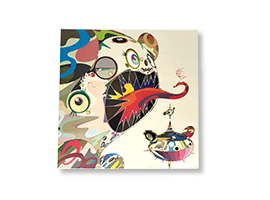
有名作家の話題をニュースなどでも目にする機会の多い現代アートについて、興味があるという人も多いでしょう。
20世紀以降に生まれた「現代アート」ですが、現在では国内外問わず多くの現代アート作家が活躍しています。
私たちの生活でよく目にする作品も多く、実は身近で触れている可能性も高いのです。
この記事では、「海外の現代アート作家を知りたい」「海外でも活躍している日本人アーティストはいるの?」という疑問をお持ちの人へ、国内外の有名作家と彼らの作品についてご紹介します。
※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。


「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!
目次
現代アートとは
「現代アート」とは、第二次世界大戦後である1950年以降に制作された作品で、これまでの美術概念に囚われていない前衛的な表現をしているものの総称です。
そのため、現代アートには作品形態や技法に囚われない多様な作品があります。
具体的には、パフォーマンスや映像といった媒体、空間や時間といった身近な概念も現代アートの素材になり得ます。
また、社会情勢などに対する問題提起やメッセージが込められた作品が多いという点も現代アートの特徴と言えます。
「現代アートは分かりにくい」と言われることも多いですが、鑑賞者が思考や洞察をして楽しむ余地があるのが1つのポイントです。
作品の制作背景や制作に至るまでのストーリー、問題提起の内容などを含めて鑑賞することで、より楽しめるかもしれません。
現代アートのジャンル
現代アートは表現方法の多様性が特徴であるため、ひとくちに現代アートと言ってもジャンルは様々です。
主なものとしては以下のようなものがあります。
- コンセプチュアルアート:技術や美的価値よりアイデアや思想を重視する
- インスタレーション:空間そのものを作品にする
- パフォーマンスアート:芸術家や参加者の実演がそのまま作品になる
- ポップアート:漫画・広告など大量消費や大衆文化の要素を取り入れる
- フォトペインティング:新聞や雑誌の写真をぼかした上で絵画に活用する
- ミニマルアート:最小限の色と形で題材を表現する
- ネオポップ:漫画やアニメなどのサブカルチャー要素を取り入れる
- 具体美術:「人の真似をするな、今までにないものをつくれ」がコンセプト
もちろん、表現方法や媒体に規定のない現代アートですから、この他にも様々な表現があり得ます。
今後も、これまでになかった新しい表現が生み出されていくかもしれません。
現代アートで有名な海外の作家15人
隆盛を見せている現代アートには、有名作家・人気作家が多数存在します。
ここでは有名な海外作家について、厳選した15人を中心にご紹介します。
- マルセル・デュシャン
- ジャクソン・ポロック
- アンディ・ウォーホル
- アンリ・マティス
- ワシリー・カンディンスキー
- キース・へリング
- イサム・ノグチ
- ジョン・ケージ
- ジェームズ・タレル
- マリーナ・アブラモヴィッチ
- ジャン=ミシェル・バスキア
- ダミアン・ハースト
- バンクシー
- KAWS
- ゲルハルト・リヒター
1人ずつ、プロフィールや作品の特徴について解説していきます。
マルセル・デュシャン
マルセル・デュシャン(1887-1968)はフランスのアーティストで、20世紀美術に大きな影響を与えた人物です。
最初はキュビズム風(ピカソの作品のような幾何学的なアート)の油絵を中心に制作していました。
しかし1917年に発表した「泉」という作品で、世界から注目を浴びます。
「泉」は男性用便器を横にして、「R.Mutt」という署名と年号の「1917」を記しているだけの作品です。
マルセル・デュシャンは、日常に存在する既製品を芸術作品に昇華させ「芸術とはなにか?」という問いを世界に投げかけました。
「泉」をきっかけに、20世紀以降の現代アートは「作品を鑑賞する者への投げかけ」を目的に作られるようになったのです。
ジャクソン・ポロック
ジャクソン・ポロック(1912-1956)は、アメリカの画家です。
数ある絵画ジャンルの中でも、抽象表現主義に分類されます。
抽象表現主義はアメリカで誕生したジャンルで、まるで幼児が遊んでいるかのように絵の具を適当にキャンバスにぶちまけたような手法を用いています。
ジャクソン・ポロックは、抽象表現主義を独自に変化させ「アクションペインティング」という技法を生み出しました。
アクションペインティングは、体を動かしながら絵の具を飛び散らせたり垂らしたりして制作する手法です。
独創的な作風で人気を博しましたが、周囲からのプレッシャーに苦しみ、長年患わっていたアルコール依存症を再発してしまいます。
そして1956年、44歳の若さで飲酒運転による事故で亡くなりました。
ジャクソン・ポロックの代表作は「男と女」「壁画」などです。
アンディ・ウォーホル
アンディ・ウォーホル(1928-1987)はアメリカのアーティストで、ポップアートの巨匠として知られています。
ポップアートとは、1960年半ば〜1970年代にイギリスとアメリカで誕生した絵画ジャンルです。
大量生産・大量消費を繰り返す現代社会をテーマにしています。
アンディ・ウォーホルの作品は、当時の有名女優やコミックスなど、大衆に馴染みのあるモチーフが多く用いられている点が特徴です。
代表作品には「狙撃されたマリリン」や「キャンベルのスープ缶」などがあります。
アンディ・ウォーホルの作品は、現在でも文房具や洋服などさまざまなものに転用されているため、どこかで見たことがある人も多いのではないでしょうか。
アンリ・マティス
アンリ・マティス(1869-1954)はフランス生まれで、フォーヴィスム(野獣派)の代表的な画家です。
自身の感情を独自の色彩感覚で描き「色彩の魔術師」とも呼ばれています。
同時期に活躍したパブロ・ピカソやマルセル・デュシャンと並んで、世界を代表する芸術家の一人です。
アンリ・マティスは油絵を中心に制作していましたが、独自の色彩と感情を追求した結果、晩年には色紙を切り貼りした「切り絵」を多く残しました。
代表作には「緑のすじのあるマティス夫人の肖像」「ブルー・ヌード Ⅳ」などがあります。
ワシリー・カンディンスキー
ワシリー・カンディンスキー(1866-1944)はロシアの画家、美術理論家です。
絵画を本格的に学び始めたのは30歳と遅いですが、抽象画の創始者として知られています。
抽象画誕生のきっかけは、クロード・モネの作品を見たことです。
当時のワシリー・カンディンスキーは「絵画は写実的なもの」という概念を持っていました。
そのためモネの作品に感銘を受けつつも、絵の意図は理解できなかったそうです。
しかし「作品の具体的な意図がわからなくても、色や形で表現できる」と考え、抽象画の作成・研究に勤しみました。
ワシリー・カンディンスキーの代表作には「コンポジションⅧ」や「印象Ⅲ」などがあります。
キース・へリング
キース・ヘリング(1958 -1990)は、アメリカ生まれのストリート・アート、グラフィティ・アートの先駆者です。
1980年代のアメリカアートを牽引した代表的な人物として知られています。
キース・ヘリングはエイズに感染し、1990年に31歳という若さで亡くなりました。
また同性愛者であったことから、彼の作品にはエイズの予防啓発やLGBTの認知など、社会問題が多く取り上げられています。
キース・ヘリングの作品は「チョーク・アウトライン形式」と呼ばれる手法を用いており、シンプルでありながら大胆な色使いが魅力です。
「ラディアント・ベイビー」や犬をアイコンにした作品が有名で、現在でも洋服のデザインなどに使用されています。
イサム・ノグチ
イサム・ノグチ(1904 -1988)は、アメリカで活躍した日系アメリカ人アーティストです。
彫刻家やインテリアデザイナーなど多くの肩書きを持っており、活躍したジャンルは多岐にわたります。
そのため代表作も非常に多く、日本にもルーツがある点から、国内にも彼の作品がたくさん残されています。
【モエレ沼公園】
北海道札幌市にある有名な観光スポットで、イサム・ノグチが設計を手掛けました。
公園全体が彼の「大地の彫刻」になっており、見どころ満載です。
【こどもの国】
神奈川県横浜市と東京都町田市をまたぐ位置にある「こどもの国」は、雑木林を中心とした公園です。
設計集団の一人として参画し、こどもの遊び場を多く作りました。
【AKARI】
AKARIは、岐阜提灯をモチーフにデザインされたランプシリーズです。
35年間で200種類以上が制作されました。
和紙の柔らかい光と優れたデザイン性が人気で、現在でも購入可能です。
ジョン・ケージ
ジョン・ケージ(1912-1992)は、アメリカの音楽家で、クラシック音楽の概念を覆した人物として有名です。
理由は、代表作の「4分33秒」にあります。
クラシック音楽は、作曲家が作った曲をオーケストラが演奏するのが当たり前でした。
しかし「4分33秒」では、オーケストラは一切演奏しません。
無音の中、その場で発生する音や空間を楽しむ楽曲です。
当時は斬新な曲として賛否両論ありましたが、現在では高く評価されており、時折クラシックコンサートなどで演奏されています。
そんなジョン・ケージは音楽家だけでなく、思想家や詩人、キノコ研究家など多彩な顔を持ち、芸術作品も世に残しました。
東洋思想への関心を深めていたことから、京都龍安寺の石庭の配置を様々な角度から方眼紙の上に投影したドローイング作品などもあります。
ジェームズ・タレル
ジェームズ・タレル(1943-)は、アメリカの美術家です。
1968年〜1971年までアメリカ航空宇宙局研究所に勤務し、現在は光と空間をテーマにしたインスタレーション作品を多く手掛けています。
彼はアメリカ在住ですが、作品は日本各地でも鑑賞可能です。
例えば石川県金沢市にある「21世紀美術館」では「Blue Planet Sky(タレルの部屋)」と呼ばれる作品が展示されています。
タレルの部屋は、石のベンチに座り、四角くくりぬかれた天井から空の様子を眺められる空間作品です。
時間によって異なる空の様子に魅了され、長時間居続けたり何度も訪れる人がいます。
マリーナ・アブラモヴィッチ
マリーナ・アブラモヴィッチ(1946-)は、旧ユーゴスラビア出身のセルビア系アメリカ人です。
パフォーマンスアートの母と呼ばれていますが、自身の肉体を酷使した過激な作品が多いため、賛否両論があります。
特に衝撃的だったのが「Rhythm 0」と呼ばれるパフォーマンスです。
「Rhythm 0」は、観客たちが用意された72個の道具を用いて、マネキンのように佇んだマリーナ・アブラモヴィッチの体に使うといった内容でした。
中には彼女の服を切り裂いて体を切りつけ、銃を突きつける観客までいたそうです。
マリーナ・アブラモヴィッチは自らの危険を顧みず、人間の残酷で暴力的な一面を表現しました。
ジャン=ミシェル・バスキア
ジャン=ミシェル・バスキア(1960-1988)は、ハイチ系アメリカ人の画家です。
彼は黒人ゆえに、幼い頃から差別や貧困に苦しんできました。
そのため作品には、根強く残る黒人差別や貧富の差に対する悲しみや怒りが込められています。
具体的には人種差別や、奴隷制度に関する事件・有名人などが作品内に直接描かれており、作中のヒーローは王冠で表現されています。
また、文章や地図記号などが多く登場する点も特徴です。
ジャン=ミシェル・バスキアはヘロインの過剰摂取により、27歳で亡くなりました。
しかし彼の作品は、大手アパレルメーカーのUNIQLOとコラボレーションするなど、現在でも多くの人に愛されています。
ダミアン・ハースト
ダミアン・ハースト(1965-)はイギリスの美術家で、生と死をテーマにした作品が多く「Natural History」と呼ばれる、サメや牛など動物の死体をホルマリン漬けにしたシリーズで知られています。
「Natural History」シリーズは美術品として高い評価を受けており、これまでに数多くの賞を受賞しています。
しかし過激でショッキングな作品ゆえ、「気持ち悪い」という感情を抱く人もいるでしょう。
彼の作品は現代アートとして人気が高く、オークションや新作の販売価格は現存する美術家の中で最も高値がつきます。
バンクシー
バンクシーは、本名や年齢などを明かさず、公の場にも現れない匿名の現代アート作家です。
型の上から塗料を吹きかける技法を使った作品が多く、壁や橋などに政治的・社会的な問題に対するメッセージを込めたアートが世界中の街角で発見されます。
バンクシーの作品で大きな話題になったのが、2018年のオークションで約1億5千万円で落札された「Girl with Balloon」です。
落札された直後、額に仕込まれたシュレッダーで裁断されたというニュースを覚えている人もおおいのではないでしょうか。
代表作としては「Girl with Balloon」のほかに、「flower bomber」「Love is in the Air」「Napalm」などがあります。
KAWS
KAWS(1974‐)は、グラフィックアートを得意とするアメリカの現代アート作家です。
大胆な色彩と、カートゥーン調のキャラクターを変形させたようなデザインが特徴と言われます。
KAWSを国際的な人気作家に押し上げたのが、オリジナルキャラクターの「コンパニオン」です。
目を「×」で表現したデザインが有名で、ユニクロやナイキなどとのコラボレーション商品のデザインとして記憶にある人も多いのではないでしょうか。
代表作としては「コンパニオン」のほかに「THE KAWS ALBUM」などがあります。
ゲルハルト・リヒター
ゲルハルト・リヒター(1932‐)は、「ドイツ最高峰の画家」とも呼ばれる現代アート界の巨匠です。
「フォト・ペインティング」(写真をもとに、それとそっくりの絵を描く手法)、「アブストラクト・ペインティング」(色を塗ったあとにスクイージーで削るなどすることで、色彩が複雑に入り混じる手法)、「オイル・オン・フォト」(写真に油絵具を塗りつける手法)など、幾度も手法を変えながら「人間が物を見る」ということを表現し続けています。
代表作としては、「1025 Farben (357-3)」「Birkenau」、ケルン大聖堂のステンドグラスなどがあります。
まだまだいる現代アートの海外有名作家
現代アートの有名作家は、ここでは紹介しきれないほどまだまだたくさんいます。
海外の作家としては、以下の表にあるような作家も有名です。
| ディヴィッド・ホックニー | ジェフ・クーンズ | オラファー・エリアソン |
| アニッシュ・カプーア | ジュリアン・オピー | ピーター・ドイグ |
| マーク・グロッチャン | ルシアン・フロイド | エイドリアン・ゲーニー |
| アンゼルム・キーファー | マーク・ブラッドフォード | ジョン・カリン |
| 李禹煥 |
世界で活躍する日本人の現代アート作家19人
現代アートの世界には、海外で活躍する日本人作家も数多くいます。
ここでは、日本を代表する現代アート作家を19人ご紹介します。
- 草間彌生
- 岡本太郎
- オノ・ヨーコ
- 白髪一雄
- 河原温
- 赤瀬川原平
- 横尾忠則
- 奈良美智
- 村上隆
- 小松美羽
- 会田誠
- 山口晃
- 千住博
- 宮島達男
- 杉本博司
- 塩田千春
- ロッカクアヤコ
- 名和晃平
- 束芋
1人ずつプロフィールや作品を見ていきましょう。
草間彌生
草間彌生(1929-)は長野県生まれの女性画家です。
1957年に渡米し、細かい網目模様を巨大なキャンバスに描いた「ネット・ペインティング」や男性器をモチーフにした「ソフト・スカルプチャー」など、さまざまな作品を発表して現代アーティストとしての地位を確立しました。
草間彌生の作品は、幼少期の幻視や幻聴体験をきっかけにした網目模様や水玉模様をモチーフにした絵画が特徴です。
これらは彼女の代名詞としても知られており、「水玉の女王」とも呼ばれています。
草間彌生の作品は国内に多く存在しており、彼女の代表作である「かぼちゃ」のオブジェは、日本各地で見られます。
また、ハイブランドとのコラボレーションなども行っており、作品を見かける機会の多いアーティストです。
岡本太郎
岡本太郎(1911-1996)は、神奈川県生まれの芸術家です。
青年期をパリで過ごし、特にパブロ・ピカソに大きな影響を受けました。
しかし、第二次世界大戦のため日本に帰国することになりました。
戦後は精力的に活動し、多くの作品を残しました。
数ある作品の中で最も有名なのは「太陽の塔」です。
1970年の大阪万博のシンボルとして作られ、高い評価を受けています。
高さ70メートルの塔の内部には「生命の樹」と呼ばれる彫刻が置かれています。
「生命の樹」は人間と宇宙、生命の神秘をテーマに、岡本太郎の創造性と独自性を表しているのが特徴です。
オノ・ヨーコ
オノ・ヨーコ(1933-)と聞くと大人気アーティストであった「ビートルズ」のジョン・レノンの妻というイメージをお持ちの方もいるでしょう。
実はジョン・レノンの妻として彼を支えつつも、彼女自身もアーティストとして活躍しています。
オノ・ヨーコは東京の裕福な家庭に生まれ、アメリカの大学で音楽と詩を学びました。
2度の離婚を経験した後、ジョン・レノンと再婚します。
ジョン・レノンの死後は彼の意思を受け継ぎ、平和活動にも力を入れています。
オノ・ヨーコの代表作品には「カット・ピース」や「ベッド・イン」(ジョン・レノンとの合作)などがあり、世界平和について訴えています。
白髪一雄
白髪一雄(1924-2008)は、兵庫県生まれの日本の抽象画家です。
活動初期は風景画や人物画を描いていましたが、独自性を求めて「フット・ペインティング」という技法を生み出します。
フット・ペインティングは天井から吊るしたロープにつかまり、足で床に広げたキャンバスに描いていく手法です。
その後も多くの作品を残しましたが、1971年には比叡山延暦寺で出家し、天台宗の僧侶に転身しました。
白髪一雄の作品で有名なのは「臙脂」です。
スターバックス・コーヒーの創始者であるハワード・シュルツのオフィスに「臙脂」が飾られており、大きな話題になりました。
河原温
河原温(1932-2014)は、愛知県生まれの美術家です。
1950年代ごろまでは国内で活動していましたが、1959年に日本を離れ、その後はメキシコやニューヨークなどを拠点にしました。
河原温は、コンセプチュアルアートの第一人者として知られています。
コンセプチュアルアートとは、1960年代後半〜1970年代に誕生した前衛芸術の総称です。
絵画や彫刻という決まったジャンルではなく、思考や構想のみでも芸術とみなしている点が特徴です。
河原温の代表作としては「Date Painting」が挙げられます。
「Date Painting」は単色で塗られたキャンバスに白色で制作年月日のみを描いた作品で、1966年1月4日からほぼ毎日制作しています。
赤瀬川原平
赤瀬川原平(1937-2014)は、神奈川県生まれの美術家です。
「心はいつもアヴァンギャルド」という言葉を残しており、ときには過激に自らの芸術を追求しました。
赤瀬川原平は武蔵野美術学校油画科に進学するも、経済的理由で退学してしまいます。
退学後も創作活動を続けていたところ、吉村益信や篠原有司男らによって結成された前衛芸術グループ「ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ(ネオダダ)」に加入しました。
ネオダダの一員として活動しながら、1963年に高松次郎、中西夏之らとも「ハイレッド・センター」を結成します。
ハイレッド・センター結成後に制作した「復讐の形態学(殺す前に相手をよく見る)」は、社会的問題を起こしながらも、彼の代表作として知られています。
横尾忠則
横尾忠則(1936-)は、兵庫県生まれのアーティストです。
神戸新聞社にイラストレーターとして入社後に独立し、以降は画家として活躍しています。
2024年には88歳になりますが、現在も精力的に創作活動を続けています。
横尾忠則の作風は、誰とも被らない唯一無二を追求し続け、さまざまな手法を取り入れている点が特徴です。
過去の作品や日本神話など、あらゆるものが絵に描かれています。
横尾忠則の作品の数々は、兵庫県神戸市にある「横尾忠則現代美術館」で鑑賞可能です。
奈良美智
奈良美智(1959-)は、青森県生まれで愛知県立芸術大学美術学部を卒業後、同大学院の修士課程を修了しています。
1988年にはドイツに留学し、卒業後はケルンに移住、2000年に帰国しました。
現在は国内外問わず、多くの国や地域で作品展を開催しています。
奈良美智の代表作には、こちらを睨んでいるかのような子どもが描かれた「ナイフ・ビハインド・バック」や、少女の連作シリーズの「Cosmic Eyes」などがあります。
村上隆
村上隆(1962-)は東京都生まれで、東京藝術大学美術研究科で博士後期課程を修了し、日本画専攻で初めて博士号を取得した人物です。
村上隆は、作品において「スーパーフラット」という概念を提唱しています。
「スーパーフラット」は、日本では「ハイ」も「ロー」もすべて同じように消費されてしまうという批判から生まれた考えです。
彼は「スーパーフラット」を表現するために、日本の「オタク文化」や「カワイイ」を積極的に作品に導入しています。
代表作には花に顔が描かれている「お花(フラワー)」や、等身大フィギュアの「Ko²ちゃん」などがあります。
小松美羽
小松美羽(1984-)は、長野県出身のアーティストです。
彼女の作品は、八百万神(やおよろずのかみ)の概念や神話に登場する神獣など、日本の伝統的な文化と現代的な芸術を融合させています。
2014年には、出雲大社に「新・風土記」を奉納します。
2015年には有田焼で作られた狛犬「天地の守護獣」が、大英博物館の日本館に永久展示されることが決まりました。
小松美羽は、今後も世界での活躍が期待される新人アーティストの一人です。
会田誠
会田誠(1965-)は、エロティックでグロテスクな作品のイメージや、鋭い社会批評を交えた挑発的な作風で知られている現代アート作家です。
1990年代から絵画・インスタレーション・映像・パフォーマンスなど多様な表現方法で作品を発表しています。
代表作には、「あぜ道」、「犬」シリーズ、「考えない人」などがあります。
山口晃
山口晃(1969-)は、成田空港のパブリックアートや東京メトロ日本橋のパブリックアートなども手掛ける有名作家です。
油絵の技法と、鳥瞰図・合戦図といった日本の伝統的な構図を使った作品が有名で、緻密で詳細な描写には定評があります。
絵画のほかに、漫画・インスタレーション・執筆業など表現は多彩です。
代表作としては、「新東都名所 東海道中 日本橋 改」「成田国際空港 飛行機百珍圖」、平等院 養林庵書院の襖絵などがあります。
千住博
千住博(1958-)は、自然の美しさや力強さを捉えた風景画を得意とする画家です。
伝統的な日本画の技法をもとにしながら現代的な要素を取り入れた作品は、壮大ながら精神的な深い静けさを感じさせるとして国内外で高く評価されています。
代表作には、「THE FALL」、アメリカ・フィラデルフィアの「松風荘」の襖絵、京都「大徳寺聚光院」の襖絵などがあります。
宮島達男
宮島達男(1957-)は、デジタル技術と伝統的な日本文化を融合させた作品で知られる現代アート作家です。
ハイテクとアートの融合を通じて時間の概念を表現する宮島達夫の作品は、国際的に高い評価を得ています。
代表作としては、「時の海」「メガ・デス」「それは変化し続ける それはあらゆるものと関係を結ぶ それは永遠に続く」などがあります。
杉本博司
杉本博司は(1948-)ニューヨークを拠点に活躍する写真家であり、現代アートを手がける作家でもあります。
杉本博司の作品は、歴史・記憶・時間といったテーマを探求しており、視覚的に美しいと同時に哲学的な問いを投げかけます。
写真を現代アートの表現手段に高めたアーティストともいわれ、確かな技術で仕上げられた作品は世界で高い評価を得ています。
代表作としては、「ジオラマ」「劇場」「ポートレイト」「Polar Bear」などがあります。
塩田千春
塩田千春(1972-)は、大規模なインスタレーション作品で国際的にも注目を集めている現代アート作家です。
自らの闘病体験から「生きることとはどういう意味なのか」「存在とは何か」という人間の根源的な問題に向き合い続けるアート作品を発表しています。
塩田千春作品の特徴的な素材として、糸と船があります。
糸は人と人との縁をつなぐもの、特に赤い糸は命をあらわす色として用いられます。
舟はまだ見ぬ世界へ導くものであると同時に、死と隣り合わせのものとして表現に使われます。
代表作には、「内と外」「どこへ向かって」「不確かな旅」などがあります。
ロッカクアヤコ
ロッカクアヤコ(1982‐)は、絵筆を使わず、ダンボールやキャンバスに手指で描く独特のスタイルが有名な現代アート作家です。
独特な質感と自由な表現、ダイナミックでエネルギー溢れる作風は国内外で人気を呼んでいます。
代表作としては、「Magic Hand」「ロッカクアヤコの宇宙戦争」や、代表的なモチーフである「瞳の大きな少女」のシリーズなどがあります。
名和晃平
名和晃平(1982‐)は、オリジナリティ溢れる作風で知られる現代の彫刻家です。
彫刻の表皮に注目した「PixCell」という新たな彫刻のスタイルは、国内外から大きな注目を得ました。
例えば名和晃平の代表作「PixCell-Deer#52」では、鹿のはく製がガラスビーズなどの透明の球体で覆われています。
これによって物体の持つ現実感が失われて映像として知覚されるようになるという、彫刻の定義を超えた柔軟な作品となっています。
束芋
束芋(たばいも:1975‐)は、映像を表現の中心としたインスタレーションを得意とする作家です。
日本の日常風景である「台所」「横断歩道」「団地」「公衆便所」といったリアルなモチーフを、浮世絵のようなタッチの手描きアニメーションで描きます。
アナログ感ある独特の表現で現代日本を表現するした束芋の作品は、国際的にも高い評価を得ています。
代表作には「dolefullhouse」「にっぽんの台所」「にっぽんの横断歩道」などがあります。
注目されている現代アートの若手作家
日本の現代アート界には、注目を集める新進気鋭の若手作家も多数存在します。
もし作品をお持ちなら、今後さらに価値があがることもあるかもしれません。
簡単にではありますが、一覧でご紹介します。
| 梅沢和木 | 沼田侑香 | 松村咲希 | Maoka Ueda |
| 高屋永遠 | Yuta Okuda | 辻野清和 | 樫内あずみ |
| &lemon | YUSUKE | seira | Kaoruko Negishi |
| 望月寛子 | Tomoko Tsuchiya | YOKO TAKAHIRA | むらいさき |
| 蟷螂子 |
価値を確かめたい現代アートはバイセルにお任せください
本記事で紹介したアーティストたちは世界的にも人気が高く、作品には高い価値がつく可能性もあります。
こういった作家の作品を持っているものの「引越しなどの都合で飾る場所がない」や、お持ちの現代アート作品に「どのくらいの価値があるか知りたい」とお考えの方は、ぜひバイセルにお任せください。
骨董品買取のバイセルは、絵画をはじめとした美術作品の買取実績が豊富にあります。
バイセルは日本全国で絵画などの買取サービスをご提供し、たくさんのお客様・リピーター様からご指名をいただいてまいりました。
バイセルの査定士は、高い専門知識と豊富な査定経験を生かして、美術作品1点1点の価値をしっかりと見極めます。
繊細なアート作品の査定なら、作品を家から持ち出す必要のないバイセルの出張査定がおすすめです。
お電話1本、手数料完全無料で日本全国への出張に対応しております。
ぜひお気軽にお試しください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら
骨董品買取をもっと見る
こんなコラムも読まれています
- 現代アートの買取相場は?買取対象の作家や高く売るポイントをご紹介!
- 絵画の買取相場は?売れる絵画の種類や価値の決まり方などを解説
- ヒロ・ヤマガタ作品の買取相場はどれくらい?買取の際の注意点を解説
- クリスチャン・ラッセンの買取相場の決まり方は?高く売るポイントと人気作品
- 西洋画の買取査定ポイント4つをご紹介!高額買取に繋げよう!
- 絵の種類の名称一覧|技法や流派による分類をわかりやすく解説
- 絵画の価値ってなんだろう?高額作品の基準を解説
- 現代美術・リトグラフは人気上昇中!高額買取のポイントまとめ
- 高額買取が期待できる版画の種類は?査定ポイントや業者選びについて解説!
- 油絵ってどんな技法?中古市場で需要が見込まれる油絵作家とは?



























