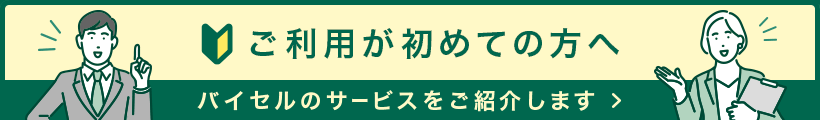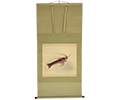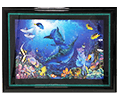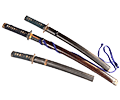荒井寛方の絵画の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説

荒井寛方(あらいかんぽう)は、深い精神性と高い品格を持った仏画で有名な日本画家です。
国内外の仏画を模写した経験によって培われた古典仏画への深い理解と、そこに近代的な日本画の描法を融合させた表現は、多くの美術ファンから非常に高く評価されています。
美術品買取市場での取引例は多くありませんが、作品のクオリティと人気から、高く買取してもらえる可能性もあるでしょう。
本記事では、荒井寛方作品の特徴や代表作・有名作品に加えて、買取市場での動向、高く売れやすい荒井寛方作品の特徴、荒井寛方の絵画を高価買取してもらうためのポイントなどについてご紹介します。
※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。


「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!
目次
荒井寛方とは
荒井寛方(1878-1945)は、明治から昭和にかけて活躍した日本画家です。
特に仏画を得意とし、国内外で文化財保護に尽力したことでも知られています。
荒井寛方は1878年、現在の栃木県さくら市に生まれました。
本名は荒井寛十郎(かんじゅうろう)です。
1899年に上京すると、浮世絵風俗画で知られる水野年方(みずのとしかた 1866-1908)に師事し、歴史画・風俗画を学びました。
「寛方」の号を与えたのも、師・水野年方です。
その後1902年に古美術雑誌『国華』を発行する国華社に入社すると、そこで古美術、特に仏画の模写に従事します。
仏教絵画の魅力や重要性を深く認識したのはこの時だったといいます。
そして1907年の第1回文展で初入選を果たすと文展で連続して入賞を重ね、仏画家としての名を高めていきます。
1916年には詩人のラビンドラナート・タゴール(1861-1941)に招かれてインドに渡り、さらにその翌年にはアジャンター壁画の模写も行いました。
この仕事は、日印文化交流の先駆的な役割を果たしたという意味でも重要です。
帰国後は仏教に画題を得た作品を中心に発表したほか、晩年には主任画家として法隆寺金堂壁画の模写事業に心血を注ぎました。
1945年に急逝したためこの模写事業は未完に終わりましたが、文化財保存の重要性を体現した行者のような存在として、のちの美術界にも大きな影響を与えています。
荒井寛方の作風
荒井寛方は初期には歴史画・風俗画も多く手掛けていましたが、なんと言っても有名なのは仏画です。
伝統的な仏画が持つ厳粛さや精神性を保ちながら、そこに近代的な日本画の描法を取り入れ、品格のある仏画を追究しました。
荒井寛方の仏画は、古美術雑誌『国華』での仏画模写や、海外での模写経験によって培われた古典仏画への深い理解に基づいているのが特徴です。
特に、インドのアジャンターの壁画の模写によって身につけた、ボリューム感のある肉体表現や豊かな曲線の表現、濃密な雰囲気などは荒井寛方ならではの特徴となっています。
色彩の面でも日本画の伝統色に加えてインドの壁画が持つ土の色や深みのある色彩を取り入れ、作品に異国情緒と独特の深みを与えています。
金泥や渋い中間色を多用することで画面全体に静謐で荘厳な雰囲気をもたらし、特に、仏像の肌を表現する際の微妙な濃淡の使い方は見事です。
描線の面でも、仏画模写を通じて習得した格調高さは特徴となっており、衣のひだや仏像の穏やかな表情を描く筆致は非常に洗練されています。
荒井寛方作品の買取価格は高い?高く売れやすいポイントとは
古典仏画への深い理解に基づく、深い精神性と高い品格を持った荒井寛方の作品には、多くの美術ファンからの高い人気があります。
美術館への収蔵が多いことなどもあって美術品買取市場での取引例は多くないのですが、買取市場に出てきた場合には高い価値がつく可能性があるでしょう。
荒井寛方作品の中でも美術品買取市場で高く評価されやすいのは、やはり代名詞とも言える観音像などの仏画です。
特に渡印後の、インドのアジャンター壁画の影響を受けた独自性の高い仏画は人気が高く、高い価値がつく可能性があります。
荒井寛方だけでなく、絵画の買取では有名作家の作品ほど買取相場が高くなりやすい傾向があります。
以下の各ページでは、有名作家の作品を中心とした日本画・掛け軸の買取相場や、高く売るためのポイントといった買取情報について記載してございます。
参考までにぜひご参照ください。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへバイセルでの日本画の買取実績は?
バイセルには、日本画をはじめとした絵画の買取実績が数多くございます。
以下の各ページでは、日本画をはじめとした絵画のバイセルでの実際の買取例について記載してございます。
参考までにぜひご覧ください。
荒井寛方の代表作
深い精神性と高い品格、そして異国情緒までを感じさせる荒井寛方の仏画は、多くの美術ファンを魅了しています。
ここでは、荒井寛方の絵画の中でも特に人気の高い、代表作と言うべき作品についてご紹介します。
乳糜供養(にゅうびくよう)
「乳糜供養」(1915)は、荒井寛方の渡印直前に描かれた、画業前期の代表作です。
東京国立博物館に所蔵されています。
「乳糜供養」は、六曲一隻から成る大作の屏風絵です。
モチーフは、長年の苦行で栄養失調に陥ったゴータマに、付近の村の娘スジャータが乳糜(牛乳で作った粥)を差し出す、仏教説話の有名なシーンです。
この乳糜の供養によって体力を回復したゴータマは菩提樹の下で座禅に入り、ついに悟りを開いて仏陀になったという、非常に重要なエピソードとなっています。
六曲一隻という大画面に描かれているのは、乳糜を捧げるスジャータの真摯な姿と、スジャータに従う4人の娘たち、そして2頭の牛です。
正確な線描と抑制された色彩が主題の持つ精神性を高めており、物語の神聖さと静謐さが見事に表現されています。
観音摩利耶(かんのんまりや)
「観音摩利耶」(1939)は、国際的な感覚を持った荒井寛方のセンスが光る、晩年の代表作です。
東京国立近代美術館に所蔵されています。
「観音摩利耶」は、三曲一双から成る屏風絵です。
そして、対になっている2つのモチーフは、なんと観音菩薩と聖母マリアです。
左隻に観音菩薩、右隻に聖母マリアと、異なる文化圏の母性像が並置されているのは大きな特徴であり、荒井寛方の国際感覚と懐の深さが伺えます。
仏教とキリスト教を作品の中で融合することによって、「仏教(仏)とキリスト教(耶)の根源的な精神は1つである」という「仏耶一如(ぶつやいちにょ)」の思想を表現しています。
制作されたのは、今まさに第二次世界大戦へと突入していくという時代です。
世界中に不穏な空気が満ちる中、荒井寛方は宗派や国境を超えた人類愛と世界平和への強い願いを込めて、この作品を制作したと考えられています。
玄奘と太宗(げんじょうとたいそう)
「玄奘と太宗」(1927)は、荒井寛方が得意とした仏画と歴史画の要素を融合させた意欲作です。
栃木県立美術館に所蔵されています。
「玄奘と太宗」は、四曲一隻から成る屏風絵です。
モチーフは、『西遊記』の三蔵法師のモデルとなった実在の僧侶・玄奘(げんじょう 602-664)がインドから帰還した際、唐王朝の第2代皇帝・太宗(たいそう 598-649)と会見した歴史上の有名なシーンです。
画面左側に描かれている玄奘は質素な僧衣に身を包み、長旅と修行によって悟りを得た者の静けさと精神的な高潔さを体現しています。
玄奘が手に持つ経典は、世俗の権力や富を超えた「聖なるもの」を象徴すると考えられます。
一方で、画面右側に描かれた太宗は皇帝を象徴する竜の文様の衣を着、格式高い冠をかぶっており、世俗の最高権力者としての威厳と華やかさを象徴していると考えられます。
この2人の人物を屏風の左右に意図的に配置し、「聖と俗」というそれぞれの世界観をくっきりと隔てるかのような対照的な構図で描き分けている点が特徴的です。
「玄奘と太宗」は、仏画の模写などを通して身につけた仏教的世界観と、水野年方門下で磨いた歴史人物画の描写力が見事に融合した、荒井寛方の本質を示す重要な作品と言えるでしょう。
暮れゆく秋
「暮れゆく秋」(1914)は、荒井寛方としては珍しい風景画の名作です。
栃木県のさくら市ミュージアムに所蔵されています。
描かれているのは、日の暮れゆく秋の里山の情景です。
広がる田園風景とその先に連なる山々のシルエットが、観る者に静かで詩的な感情を呼び起こします。
色彩の面では、黄昏時の淡い光と、それに染まる深みのある色彩が特徴です。
全体的に落ち着いたトーンでまとめられ、画面全体に静謐で感傷的な空気感が満ちています。
また、遠景の山々と近景の里山の描写が明確に分けられ、奥行きのある広大な空間が表現されています。
仏画を得意とした荒井寛方が風景画でもこのような傑作を残しているという点は、荒井寛方の卓越した技量を証明していると言えるでしょう。
ほかにも「龍虎図」「魚籃観音」「聖観世音菩薩像」「羅浮仙」など、荒井寛方には数多くの人気作品があります。
また、ここに名前のない作品であっても、荒井寛方作品であれば保存状態などの条件によって買取してもらえる可能性があります。
お持ちの荒井寛方作品の具体的な価値については、ぜひ1度バイセルの無料査定でお確かめください。
お問い合わせ・無料相談はこちら
電話から相談する
0120-612-773
通話料無料・24時間365日受付中
メールから相談する
お申し込みフォームへ荒井寛方の絵画を高価買取してもらうためのポイント
古典仏画への深い理解に基づく、深い精神性と高い品格を持った荒井寛方の仏画は、多くの美術ファンから高い価値が認められています。
では、荒井寛方の絵画を少しでも高く売るためにはどのようなポイントに気をつければ良いでしょうか。
荒井寛方作品を含む絵画の買取において、より高く買取してもらうために知っておきたい3つのポイントをご紹介します。
- 綺麗な状態で保存しておく
- 鑑定書などの付属品を揃えておく
- 入手経路などの来歴を明確にしておく
綺麗な状態で保存しておく
荒井寛方を含む絵画の買取では、保存状態が良好である(制作当時の状態をなるべく保っている)ほど高く買取されやすい傾向があります。
反対に、ひび割れ、退色、シミ、シワ、カビ、傷、破れ、タバコの臭いがあるなど保存状態が悪いと、その分だけ買取価格は下がってしまいます。
荒井寛方のような有名作家の場合には多少の経年劣化があっても買取してもらえる場合も多いですが、高価買取の可能性は低くなってしまうでしょう。
作品を良い状態に保つためには、専用の袋や箱で保護する、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管するなどの工夫をしてあげましょう。
鑑定書などの付属品を揃えておく
荒井寛方のような有名画家の作品をより高く売るためには、作者のサインや鑑定書・保証書といった、作品の価値を示す付属品の有無が重要な役割を果たします。
荒井寛方作品の場合、作品の右下などに「寛方」の署名と朱色の印章が押されているものが多いです。
また、模写作品では「寛方敬写」の署名に朱色の印章が入っているケースが多いです。
これらのサインや印章は作品の品質と信頼性を示す重要な証拠になるため、買取市場における信頼性が増すことで多くの需要を集められます。
鑑定書も同様の効果があり、付いていることで作品の価値を証明できるため買取市場における信頼性が増します。
これらがあることで、より高い価格での買取につながる可能性があります。
鑑定書・保証書などの付属品がある場合には、作品本体と併せて大切に保管しておきましょう。
入手経路などの来歴を明確にしておく
荒井寛方をはじめとした絵画の査定では、買取市場における作品の信頼性のために「どこで手に入れたか」「いつ購入したか」「誰から譲り受けたか」など購入に至るまでの背景が確認されます。
例えば「業界で信頼されている専門店で購入した」「〇年△月に××博物館に貸し出した」などの来歴は、作品の価値を判断するうえでも重要な情報になります。
そして、その来歴を証明する書類等があればさらに信憑性が増し、買取市場における信用度が増すことでより高く売れるかもしれません。
入手した経路や時期、美術館への貸出履歴といった記録がある場合には、処分せずに大切に保管しておきましょう。
荒井寛方作品を売るなら買取実績豊富なバイセルへ
荒井寛方の絵画の買取をお考えなら、骨董品買取のバイセルにお任せください。
バイセルは日本全国で骨董品・美術品などの買取サービスをご提供し、たくさんのお客様・リピーター様からご指名をいただいてまいりました。
バイセルの査定士は、高い専門知識と豊富な査定経験を生かして、荒井寛方作品をはじめとした絵画1点1点の価値をしっかりと見極め、正確に鑑定します。
バイセルの出張買取ならお電話1本、手数料完全無料で日本全国への出張買取に対応しております。
「試しに価値がどれくらいか聞いてみたい」「傷や汚れがあって売れるか不安」といった場合にも無料でご相談いただけます。
ぜひ1度お気軽にお試しください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら
骨董品買取をもっと見る
こんなコラムも読まれています
- 秋野不矩作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 池上秀畝作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 大山忠作作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 小川芋銭作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 小野竹喬作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 大橋翠石作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 奥田元宋作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 浦上玉堂の絵画の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 岩田専太郎作品の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説
- 今尾景年の絵画の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説