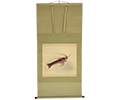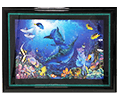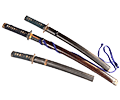掛け軸の基本知識とおしゃれに飾るために知っておきたいポイント

床の間に掛け軸も生け花もないまま、デッドスペースになっているケースは少なくありません。
せっかくの床の間があるのだから、掛け軸を飾って和室を華やかに彩ってみてはいかがでしょうか。
本記事では床の間と掛け軸の基本知識、掛け軸を飾る時に必要な準備、取り扱い方、そして掛け軸の種類、保管方法などを詳しく紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。
床の間と掛け軸の基本知識

床の間とは、和室にある一段高くなった空間です。
最も格式高い部屋に作られており、掛け軸や生け花などで装飾して来客をもてなします。
また、床の間の歴史は奈良時代から始まります。
床の間は身分の高い人が座る場所として畳よりも一段高く作られていましたが、江戸時代には庶民にも普及して今の床の間となりました。
ちなみに床の間に背向けて座る席が、最も上位の席とされています。
一方、掛け軸とは書や絵を観賞用に装飾したものです。
昔は飾るものではなく拝むものとして利用されていました。
いつしか季節の花が描かれた作品や美しい言葉が記された作品などを部屋に掛け楽しむようになり、掛け軸は飾るものとして認識されるようになりました。
掛け軸や生け花は、和室を彩る定番の装飾品です。
季節に合わせて掛け軸の種類を変えて、来客をもてなすという意味で飾ります。
他にも家内安全、夫婦円満、健康長寿を願ったり、運気アップといった風水的な意味を込めています。
床の間と掛け軸のサイズを測っておこう

これから床の間に掛け軸を飾りたいと考えている方に向けて、掛け軸を飾るのに必要な準備や取り扱い方について以下の3つのポイントをご紹介します。
- ・床の間のサイズを測る
- ・掛け軸のサイズを測る
- ・掛け軸のかけ方
掛け軸は床の間とのバランスによって、見え方が変わります。
掛け軸を美しく見せる基本的な知識を知っておきましょう。
床の間のサイズを測る
まず、床の間のサイズを測ります。
掛け軸は、床の間の横幅に対して約3分の1の幅が美しく見えるサイズと言われています。
また、床の間の長さは180cm〜190cmが標準サイズといわれていますが、丈が短い掛け軸もあります。
床の間のサイズがわかったら、次に掛け軸のサイズを測ります。
床の間と掛け軸のサイズの具体例
床の間を美しく飾るポイントとして、掛け軸と床の間のバランス感は非常に重要です。
以下に、床の間のサイズに合った掛け軸のサイズの種類を表にしました。
| 床の間のサイズ | 掛け軸のサイズ |
|---|---|
| 横幅が一間(約180cm) | 尺五立(61m×191cm) |
| 尺八立(71cm×194cm) | |
| 横幅が半間(約90cm) | 半切立(51cm×181cm) |
| 尺巾立(47cm×181cm) | |
| 下に棚や窓がある床の間 | 尺五横(61cm×142cm) |
| 尺八横(71cm×136cm) |
床の間の横幅が約180cmなら、掛け軸のサイズは一般的な「尺五立」や少し幅広い「尺八立」が合います。
床の間の横幅が約90cmなら、書の掛け軸に多いサイズの「半切立」や尺五立より幅の狭い「尺巾立」が適しています。
また、下に棚や窓がある床の間なら「尺五横」や「尺八横」が合います。
尺五横は長さの短い掛け軸で、床の間の高さが低い方に最適です。
尺八横は尺八立よりも長さが短いものです。
床の間がなくても掛け軸はかけられる!
掛け軸は床の間や和室以外に掛けてはいけないというマナーはありません。
飾る場所を選ばずに楽しめるのは、掛け軸の魅力のひとつです。
例えば、床の間がないマンションのリビングでも掛け軸を楽しめます。
掛け軸を直射日光の当たらない場所に掛けて、その下に畳を敷き、和雑貨や生け花を置くだけで床の間風の空間ができます。
他にも洋室に合う掛け軸や絵画を印刷した洋風の掛け軸など、様々な種類の商品が販売されています。
掛け軸は床の間がなくても部屋の雰囲気に合わせて楽しめる古美術です。
掛け軸をかける手順

掛け軸のサイズが決まったら、掛ける時の注意点をご紹介します。
掛け軸は非常に繊細な美術品ですので、丁寧に取り扱いましょう。
- 1、掛け軸を巻いているヒモの端を持ってゆっくりと引く
- 2、巻ヒモを掛け軸の後ろに回して、右端に寄せる
- 3、自在(じざい:掛け軸の高さを調節する道具)を上から吊るして、飾りたい掛け軸の高さにに合わせて駒をセットする
- 4、矢筈(やはず:掛け軸をかける時使う棒)に掛け軸の上のヒモを引っ掛ける
- 5、反対の手で丸めたままの掛け軸の下を支えながら持ち上げる
- 6、自在に掛けヒモを掛けたら、両手で掛け軸の両端を持って下ろす
- 7、下ろしたら太巻芯を外す
- 8、全体のバランスを確認して、掛け軸の下に風鎮(ふうちん)を掛ける
掛け軸をかける際のポイント
大切な掛け軸を長く使うためのポイントを3つご紹介いたします。
1、掛軸に影がかからないようにする
2、矢筈(やはず)を使う
3、掛け軸は両手で下ろす
掛け軸に影がかからないよう掛けます。
床の間は影にならないように配置されていますが、掛け軸の前に壺や花瓶を置いた場合だと光源によっては掛け軸に影がかかってしまう場合があります。
掛け軸の前に物を置く場合は光の向きに気をつけましょう。
矢筈とは掛け軸を掛ける時に使う棒です。
掛け軸を高い位置に掛けるときに踏み台を使わずに掛けられます。
掛け軸が曲がっていたり、高さのバランスが悪いと部屋の印象が悪くなりますが、矢筈があると細かい調整ができて便利です。
掛け軸は繊細な美術品ですから破損しないよう、下ろす時は両手でゆっくりと巻きおろしましょう。
掛け軸をしまう手順
- 1、太巻芯を軸棒に取り付けて、両端を持ちながらゆっくり巻き上げる
- 2、胸の高さまで巻き上げたら、掛け軸中央を片手で持ち替えて矢筈で下ろす
- 3、畳の床など広い場所に広げた状態で、最後まで巻き上げる
- 4、最後に巻緒で掛け軸を止める
- 5、桐箱へ収納して、スキマに防虫剤などを入れて虫食いを防ぐ
掛け軸は紙でできているので古くなると破れやすくなります。
しまうときに強く巻きすぎると折れてしまったり、シワになってしまいます。
ですから、優しくゆっくりと巻きましょう。
優しく巻きすぎて箱に入らない時は、一度開いてゆっくり巻き直します。
紙の部分は触らないように、丁寧に巻きます。
掛け軸を扱う際に避けること

長く掛け軸を楽しむには、以下にある掛け軸を扱う際に避けた方が良いことを知っておきましょう。
- ・掛け軸をしまうときは湿気とカビを避ける
- ・掛け軸が乾燥する場所に飾らない
- ・床の間に掛けたままにしない
- ・箱にしまいっぱなしも避ける
掛け軸をしまうときは湿気とカビを避ける
紙でできた掛け軸は湿気に弱いです。
箱にしまうタイミングは少しでも湿気の少ない晴れた日を選ぶと良いでしょう。
梅雨のような湿気が多い時期は、晴れた日に陰干しして乾燥させて一旦保管して、再び別の晴れた日に再度陰干しすると防げます。
ただし、濡れた手で触るとカビの原因になるので、しっかり水分を拭き取った手で作業しましょう。
薄い和紙で掛け軸を包んで、桐箱に入れたら直射日光の当たらない乾燥した場所に保管することをおすすめします。
特に桐箱は、掛け軸の収納に最適です。
桐には防腐力の高いタンニンや昆虫を寄せ付けない成分(パウロニンやセサミンなど)があるため、湿気を吸い取って虫も付きにくくなります。
掛け軸が乾燥する場所に飾らない
湿気に弱い掛け軸ですが、乾燥しすぎてもよくありません。
冷暖房が直接あたる場所だと、掛軸を乾燥させてしまって折れの原因になります。
また、ハロゲン灯の近くに飾るのも乾燥が進んでしまうので避けて下さい。
一緒に塗り物や木工芸品を置いていたら痛んでしまいます。
床の間に掛けたままにしない
1年中、掛け軸を飾ったままにすると乾燥によって折れやすくなり、日光によって焼けの原因になります。
ですから、数ヶ月に一度は別の掛け軸と交換させると長持ちします。
箱にしまいっぱなしも避ける
掛け軸は飾ったままでも、箱にしまいっぱなしでも定期的に箱の外に出さないと湿気がこもってしまうので避けた方が良いです。
使用頻度が少ない掛け軸は年に1〜2回、よく晴れて乾燥している日に虫干ししておきましょう。
床の間にかける掛け軸の種類

ここからは、掛け軸の種類について細かくご紹介します。
昔ながらの季節感のある掛け軸だけでなく、和モダンの現代風掛け軸もあります。
これから掛け軸を購入する方はぜひ参考にしてください。
季節を表す掛け軸
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 春「桜」 | 桜と鳥や桜と月がセットで描かれているものが多く、新しい気持ちで春の訪れを祝うという意味が込められています。 |
| 夏「朝顔」 | 朝顔は浴衣にもよく利用されている夏の花絵です。青を基調とした夏らしい爽やかな雰囲気があります。 |
| 秋「紅葉」 | 紅葉には小鳥の組み合わせの図柄が多く、真紅に染まる紅葉は鮮やかで趣深い秋を象徴する図柄です。 |
| 冬「水仙」 | 清楚に咲く白い水仙の花は、春を待ちわびる冬の図柄です。 |
季節の花の図柄が描かれた掛け軸を掛けることを、季節掛けといいます。
季節ごとに違う種類の掛け軸で部屋を飾るのは風情があり、掛け軸の醍醐味でもあります。
なお、季節掛けに使われる掛け軸は、季節の花と鳥がセットで描かれていることが多いです。
慶事の掛け軸
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 松竹梅高砂 | 夫婦和合・長寿などの縁起の良い図柄です。結納や婚礼の席で掛けたり、記念日の贈り物などに選ばれます。 |
| 松竹梅鶴亀 | 松竹梅は生命力の強さの象徴、鶴亀は長寿の象徴と言われ、還暦・古希などのお祝いの場や贈り物として人気です。 |
正月、結納、お祝いなどのおめでたい席を演出するに相応しい図柄を掛けます。
慶事で使用する掛け軸の中でも特に代表的なものが「松竹梅高砂」と「松竹梅鶴亀」の2つです。
仏事の掛け軸
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 松竹梅高砂 | 夫婦和合・長寿などの縁起の良い図柄です。結納や婚礼の席で掛けたり、記念日の贈り物などに選ばれます。 |
| 松竹梅鶴亀 | 松竹梅は生命力の強さの象徴、鶴亀は長寿の象徴と言われ、還暦・古希などのお祝いの場や贈り物として人気です。 |
仏事の掛け軸は、お盆、お彼岸、法事などで飾り、宗派に合わせるのが一般的です。
仏事用の掛け軸で特に有名なものは、「観音様」と「六字名号」です。
年中用の掛け軸
年中用の掛け軸は、季節を気にせず掛けられます。
洋風の部屋でも和の雰囲気を楽しみたい方に向けてモダンな掛け軸もあります。
| 掛け軸 | 特徴 |
|---|---|
| 水墨山水 | 墨で描かれた山水画は、作者の物語が描かれていることが多いです。掛け軸の中でも最も良く目にします。 |
| 書画 | 文字だけ・文字と画の入った掛け軸です。季節に関係なく飾れて人気です。 |
| 茂木蒼雲「竹に雀」 | 竹と雀を描いたモダンな雰囲気が印象的です。季節関係なく、壁にかけるだけで手軽に和の雰囲気が楽しめます。 |
| 小川光章「タペストリー・花」 | 麻を使った書の掛け軸で、季節のうつろいをイメージした作品です。リビングの間接照明などにも合う、現代風の掛け軸です。 |
おしゃれな掛け軸
インテリアアイテムとして楽しめるおしゃれな掛け軸もあります。
有名な絵画をモチーフにした掛け軸は、絵画をコレクションするのは敷居が高いけれどポスターのように飾れるので人気です。
| おしゃれな掛け軸 | 特徴 |
|---|---|
| ゴッホの「夜のカフェテラス」 | ゴッホの代表作を掛け軸にしたものです。和室や床の間がなくても掛け軸を楽しみたい方にはぴったりです。また、ナチュラルインテリアとしても人気です。 |
| 赤富士 「朱映富嶽」 | 外山寿福の作品で、吉祥図の赤富士をモチーフにした掛け軸です。事業発展や良縁に良いインテリアとしても人気です。 |
風水を意識した掛け軸
最後に風水を意識した掛け軸をご紹介します。
風水は中国発祥ですが、中国には床の間がありません。
凶の方角に作られることが多い床の間には、縁起の良い掛け軸を置くことで運気がアップするといわれています。
| 風水を意識した掛け軸 | 特徴 |
|---|---|
| 四神相応図 | 風水で使用される中国の霊獣「四神」が描かれた掛け軸です。良い運気の流れを取り込むと言われています。商売繁盛、夫婦円満、長寿、厄除けなどの意味が込められています。 |
まとめ
床の間に掛け軸を飾る時は、床の間のサイズだけでなく掛け軸のサイズもサイズを測る上で、バランス良く飾るのがポイントです。
昔からのルールに合わせて飾るのも日本らしい風情があっていいですが、床の間がないマンションのリビングなどでも、掛け軸を掛けるだけで和風モダンな雰囲気に変わります。
現代的なデザインの掛け軸もたくさん販売されていますので、床の間や和室がない方も、自分らしい和の空間を作って楽しんでください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら
骨董品買取をもっと見る